 |
| Photocuisine / Alamy |
| 専門店ならではの手打ちパスタも、19世紀以降は孔の空いた円盤から機械で押し出す製法が主流になった。これを刻んで乾かし、使いやすく包装する。 |
シチリア島にはこんな伝説がある――島を征服したアラブ人のアサド・イブン・アル・フラットが、827年に島の南岸に上陸した当時、最初の任務が、部隊のために食料をかき集めることであった。 アサドの料理人は直ちに現地の食材を吟味し、入江でイワシを捕り、近くの丘陵で山菜のフェンネル、スグリ、松の実を採り、それらすべてを、当時のヨーロッパでは知られていなかったある食材と合わせて料理した。アラブ人の侵略者はやがてこの食材を船倉に積んで持ち帰った。 パスタの伝来である。
今日、イワシのパスタは、シチリアの名物料理である。 だが、パスタがイタリア料理の主食となったいきさつを示唆するこの伝説は、マルコポーロが13世紀に中国の麺を発見したという、スパゲッティよりも長く語り継がれてきた説と比べると、知名度はかなり低い。
そもそもポーロは旅行記の中で、実際に東方で食べた麺について触れ、「イタリア各地で食べたものと同じくらい美味」と、バーミセリやラザニアになぞらえた。 また、ポーロの旅のかなり前に、イタリアではパスタの輸送と製造を記録した商業文書が見つかっている。 最も説得力のあるのは、学者らがポーロの話は北米パスタ製造業者の業界誌『マカロニ・ジャーナル』の編集者が1920年代後半に発表した作り話であると指摘していることである。
 |
| 英国図書館 |
| この絵は、16世紀半ばにタブリーズで制作された挿絵の傑作集、ニザミの『ハムサ』に収められている。 12世紀のペルシャ叙事物語、マジュヌンの物語のエピソードが描かれている。鎖に繋がれているのはマジュヌンの到着をテントで待つライラだ。 作者のミール・サイッド・アリは、背景右上に4人の料理人を描いている。 一人が肉を火にかけ、一人がその火の番をし、一人がボウルを持ってくる。女性が両手で「レシュテ」(ペルシャ語でパスタ)らしきものを練っている。 |
アサド・イブン・アル・フラットの話は架空だとしても、パスタが中東から伝来したことを示唆する証拠はある。 だが、東から西への慎ましい麺の旅物語は、フジッリのように曲がりくねり、つかみどころのないものが多い。
形(イタリアのフードライター、オレッタ・ザニーニ・デ・ヴィータの学術書『パスタ百科事典』では300以上の形状が確認されている)や風味(かぼちゃ味からイカスミまで)こそ異なるが、パスタは小麦粉と水で作った生地を伸ばし、切り、沸騰した湯で茹でて作るのが基本だ。 この最後の「茹でる」というステップが、焼いたり揚げたりして作るパンとパスタが区別される点だ。 もう一つ、粉に使う麦の種類でも区別できる。
パスタは一般的に硬いデュラム小麦(Triticum turgidum var. durum)から作られる。デュラム小麦はグルテンが豊富だが、グルテンは製造工程でも茹でる際にもパスタの形状を維持させるのに役立つ存在だ。 普通小麦(Triticum vulgare)よりもグルテンが30パーセントほど多く含まれ、水分量も低いデュラム小麦と水を混ぜて成形し乾燥させると、硬いが水で戻せる食品ができあがる。これがイタリア語でパスタセッカ、つまり乾燥パスタだ。 ここにもう一つ、大きな違いがある。
パスタフレスカ(pasta fresca)とはフレッシュなパスタ、その名の通り生麺である。 柔らかく、しなやかなパスタフレスカは、すぐに調理しなければならない。 デュラム小麦で作ることもできるが、普通小麦で作った中力粉のほうが手打ちで扱いやすいという料理人が大半で、卵を入れてまろやかにすることもある。 一方パスタセッカは、スーパーでよく見かけるようなパスタで、デュラム小麦でしか作ることができない。なぜならデュラム小麦には、半永久的な保存を可能にする独自の性質があるからである。 14世紀には、マムルークの公務員アル・ウマリが政府の報告書を引用し、北アフリカのデュラム小麦は「サイロで80年間保存がきく」とし、11世紀にはアンダルシアの地理学者アル・バクリが、トレドの特徴の一つとして、「(トレドの)小麦は何年たっても変形しなければ、腐りもしない」と自慢げに記している。
 |
パスタ以外にも、デュラム小麦は北アフリカ・アラブ料理でクスクスに最も広く使われている。クスクスは粗く挽いた乾燥セモリナ粉の生地で作る。 北アフリカの主食であるクスクスは、南欧とくにシチリアでも人気があり、パレルモではトラットリア(大衆食堂)の定番メニューだ。現代シチリア人の多くはクスクスを主食だと考えている。 一方、全粒デュラム小麦は中東全体でもブルグル(「穀物を叩いたもの」を表すペルシャ語を語源としたアラビア語の言葉)として人気を博している。ブルグルはデュラム小麦を蒸すか、または湯通しして乾燥させたものを砕いて作る。 タブーリやキッベ、ピラフといった料理に欠かせない材料だ。 チュニジアでは「ボルゴル」、サウジアラビアでは「ジャリーシュ」と呼ばれ、特にナジドや東部州のアル・ハサ・オアシスで重用されている。 ヨルダンでは、ブルグルが時には国民的ラム料理「マンサフ」でコメの代わりに使われることもあり、またエジプトとシリアでは、熟していないデュラムを煎って作った「フリカー」と呼ばれるものが、ピラフやスープにナッツのような風味とコクを与えている。
|
パスタの起源をたどる鍵はゆえに、次の3つの質問に共通する答えに集約される。 誰がデュラム小麦を育てたのか。または少なくとも定期的に手に入れることができたのか。 誰が最初にデュラム粉を生地にし、成形し、乾燥させたのか。 そして誰が成形して保存したものを茹でる方法を考案したのか。
千年前にさかのぼってみよう。 世界最古の栽培穀物の一つ、デュラム小麦は、エマー小麦の自然突然変異または自然交配として紀元前7000年に出現した。エマー小麦は肥沃な三日月地帯原産の野草であり、およそ1万年前に収穫された最初の穀草の一つである (今日、エマー小麦はスペルト小麦として知られている。イタリア語では「ファッロ」)。 デュラム小麦は保存期間が長いのに加え、いわゆる裸麦なのがメリットだったようだ。 つまり、実を包む皮が、脱穀中にもみ殻として剥がれやすい。 デメリットは、製粉してできるセモリナ粉は、軟質小麦でできた柔らかくサラサラの中力粉と比べて、粒が大きく硬い点だ。 世界で初めてパンを焼いた人がどこの誰であれ、 軟質小麦はパンに向いており、デュラム小麦はお粥や全粒粉を混ぜた料理、最終的にはパスタに適しているという性質は、きっと作り手の目にも明らかであっただろう。
パスタ材料として秘められたポテンシャルを持つデュラム小麦は、中東の起源(肥沃な三日月地帯の可能性が最も高い)から、遠く広い世界へと普及していった。いつ、どれだけ遠くまで広がったかは、史学者と古植物学者の研究対象だ。 麺が最初に作られたのは中国であるとされることが多いが、中国では確かに紀元前2500年に小麦が栽培されていた。だがこれはデュラム小麦とは違う。 それは普通小麦であり、人類学者は一般的にこの小麦とその製粉技術は、シルクロードを経て西アジア人が中国にもたらした可能性があるとの見解で一致している。 ミュンヘン大学中国研究部門の創設者で、『ケンブリッジ中国史』の著者、故ヘルベルト・フランクによると、言語学者は、中国では多くの非中国系食材に「アラビア語やペルシャ語から借用した中近東系の名前がついている」ことに気づいたという。
 |
| ジョルジオ・プサキス / Alamy |
| 1900年にアメリカで作成された5種類のデュラム小麦のイラスト。デュラム小麦に含まれる豊富なグルテンがパスタの形状維持を助けることから、「マカロニ小麦」と呼ばれている。 |
「麺やラビオリはじめ小麦でできた食べ物を表す言葉はすべて、トゥルク語の[sic]である点に注目したい」とフランクは記している。 「料理自体は中国由来ではなく、中近東から中国にもたらされた可能性が高いことがわかる。 つまり、中華料理に欠かせず、家庭料理の定番である 餃子 のような料理は、「南蛮人」が中国にもたらしたのかもしれない。」
中国では 紀元前 3世紀の前漢時代には麺 が作られていたことが知られているが、初期の中華麺はパスタセッカ(乾麺)ではなくパスタフレスカ(生麺)であったことを示唆する証拠がある。 12世紀になると、中国人旅行家の趙汝适が、ムスリム統治時代のスペインにおいて、小麦が「サイロで何年も劣化せずに保存できる」とされたことを不思議そうに記している。祖国でデュラム小麦に馴染みがなければ、このような発言はありえない。 東アジア人は、米など小麦以外の粉も使って麺を作った。 ポーロは、インドネシアのスマトラ島で出会った麺に驚きを隠さなかった。この麺は木からとった粉(farina di alberi)、すなわちサゴヤシかパンノキの髄から採るでんぷん質でできていた。 ポーロがイタリアにサンプルとして持ち帰ったのは、パスタセッカではなくこうした「異国風」の麺であった。
 |
| 上: フォトサーチ / フェルドマン&アソシエーツ 下: Imagebroker / Alamy |
| 人間は少なくとも8千年前からデュラム小麦の存在を知り、栽培してきた。 |
ギリシャやローマなど西を見ると、古い文献の多くで、デュラム小麦だと考えられているものに数々の言及がなされている。また、ギリシャ・ローマ世界にデュラム小麦が早期から存在していたことを示す考古学的証拠もある。 その多くが医学文献であった。 2世紀ギリシャの医者ガレンは、デュラムの味を麦の味に例えたが、「セミダリス」は食べないよう読者に注意を促している。「セミダリス」はセモリナを表すメソポタミア語の「サミド」または「セミドゥ」から派生した。
だがほとんどの文献では、今日の栄養学と同様に、デュラム小麦は食物繊維が豊富だとしている。 1世紀ローマの農学者で、シリアでは護民官であったコルメラの報告によると、デュラム小麦は北アフリカやシチリアのような乾燥気候で最もよく生育する。また、フィレンツェにある農業研究アカデミーの現代農学者レンゾ・ランディは、地元で造幣された硬貨には、デュラム小麦の稲束が描かれており、その芒の長さでデュラム小麦と特定できると指摘した。 こうした硬貨の存在により、「デュラム小麦はローマ共和国時代に確かに存在していた」とランディは述べている。
 |
イタリア人は、パスタという総称が用いられる前からパスタを食べていた。 「パスタ」 という言葉は、ペーストや生地、ペイストリーを意味するラテン語の言葉がそのまま変化せずに伝来したものだ。 このラテン語も、穀物と水でできた軽食に塩をかけた 「パストス」 を表すギリシャからの借用語である。そして「パストス」もまた、ギリシャ語で「振りかける」という意味の「パセイン」 から来ている。 現代的な意味の「パスタ」の記述で一番古いのは、1584年にウルビーノ公国の執事、ジョヴァン・バッティスタ・ロセッティが記した晩餐会を主催するための手引書だ。
それまでは、パスタを具体的な形状で呼ぶのが一般的であった。 最もポピュラーだったのが、ニョッキ(団子状のパスタで 「木の節目」を意味する「ノッキオ」から派生)と、ラザニア(「平板」の意味)、バーミセリ(「小さな虫」)、タリアテッレ(ひも状の麺、ひも状に切り取った麺。「切る」という意味の タッリャーレ から派生)、トルテリーニ(「小さなパイ」)、そしてラビオリで、これらは全て手作りされた。ラビオリの語源は不明だが1100年には「ラビオロ」として言及があり、その1000年前にはイブン・ブトランが 「サンブサジ」 として説明している。肉を生地で包んだペルシャ料理、サンブーサに調理の起源(語彙的な起源ではないとしても)がありそうだ。
「ヌデル」 (ヌードル)は18世紀のドイツに由来し、さらにスーパーで売られているような現代パスタの様々な形状は、主に19世紀の工業用押出成形技術が可能にした。円形、ひも状から車輪、アルファベットまで、様々な形の孔が開いたダイカスト銅の円盤からパスタ生地を押し出して作る。
パスタを表す名前はいろいろあるが、最も一般的なのが 「マカロニ」 またはイタリア語の 「マッケローニ」 だろう。 具体的な形状(短い、筒状、曲がった形)から総称(長いものも短いものも、筒状のものも平たいものも、ひも状のものも曲がったものもすべて)まで、幅広い意味を持つ多目的な言葉だ。 例えば、マエストロ・マルティーノの「シチリアのマカロニ」はひも状で、「ローマのマカロニ」(ローマ流の)はフェットチーネのように長く平たいものであったが、マカロニまたはマケローニの初期の記述では、丸くて短いニョッキのようなパスタとされた。 この丸い形状であれば、『デカメロン』の奇抜なシーンで描かれたような、すりおろしたパルメザンチーズの山を「マッケローニ」が落ちていく様子も説明がつく。 「マッケローニ」や「バーミセリ」という言葉は、13世紀にユダヤ系イタリア人が記した文書で初登場する。
 |
| サミュエル・ヒエロニマス・グリム / V&A美術館 / ブリッジマン・アート・ライブラリー |
| ファッションだけでは飽き足りず: マカロニクラブのメンバーらしき18世紀の英国紳士がポーズを決めている。 |
その広い用途と知名度にもかかわらず、「マカロニ」の語源は依然として謎に包まれている。 一般的にラテン語で「打つ、つぶす、こねる」を意味する「マッカーレ」から派生していると考えられており、生地を練る行為を示唆する。「マッカーレ」は「粉砕する、押し合う」という意味の「アッマカーレ」というイタリア語に残っている。 (シチリア島とプグリアでは、「マッコ」という空豆をピューレ状にして作った名物料理がある。) 同じ言葉の痕跡が、破片を意味するイタリア語「マカリエ」、そしてアーモンドパウダーで作った菓子「マカロン」にも見られる。
ギリシャ起源説もある。 パスタセッカが西欧に伝来した時期と同じ3世紀から8世紀にかけて、地中海東部の訛りである後期ギリシャ語では、「大麦と水で作られた食べ物」を意味する「マカリア」(makaria)という言葉があった。 「マカリア」は、ホメロス風ギリシャ語の「マカリオス」(祝福される者)から判断して、「祝福されし者の食べ物」とも訳される。 イタリア南部が古典ギリシャ語圏であったとき、葬式で出された細い麺のスープが「マカリア」(macaria)または「マカリア・アイオニア」(macaria-aionia、祝福されしものの永遠の食べ物)と呼ばれた。 1548年になると、モデナの医者オルテンシオ・ランドが『イタリアで最も特筆すべき、最も途方も無い事物へのガイド』で、マカロニがギリシャ・シチリアにルーツがある可能性を称え、羨ましそうに友人にこう伝えている。「風向きが変わらなければ君は一ヶ月以内に、かの豊かなシチリア島に到着するだろう。そして「列福」をその名の由来とするマッケローニを食すことだろう。」
「マカロニ」は料理と演劇のつながりにもヒントとなるかもしれない。 古代ローマで下層階級が楽しんだ道下芝居集であるアテルラナ笑劇では、マックスという名の道下が登場する。 中世イタリアでは、マックスを思わせるような滑稽なしぐさをする愚かでドジな人物が「マッケローネ」と呼ばれた。 マックスは、イタリアのルネサンス期に人気を博した街頭演劇で、仮面をかぶった即興演劇の一形態、「コメディア・デラルテ」に登場する悪党プルチネッラのモデルともなった。 プルチネッラが被った尖った鼻と白黒の仮面は「マッコ」と呼ばれ、彼の看板である小道具の中には山盛りのマカロニと大きな木のスプーンもあった。 パスタは大食いを象徴し、スプーンにはプルチネッラの暴食に応じる役割と、暴食を止めようとするものを叩く役割の二つがあった。 17世紀にはプルチネッラはプンチネッロとしても知られるようになった。さらに北へ旅し、人形劇「プンチとジュディー」の登場人物、プンチとなる。プンチはマカロニは手放したが、スプーンは手元に置いて、自分と同じくらいけんか腰の共演者を叩くのに使った。
マカロニから愚か者を連想する傾向は、大西洋を渡り、アメリカ革命戦争の愛国歌としてよく知られる「ヤンキー・ドゥードル・ダンディー」にも登場する。 エリザベス女王時代のイギリスでは、イタリアの流行と料理、習慣は、俗っぽい雰囲気を出したい人々のお決まりの流儀だった。 中には度が過ぎる人もいた。18世紀になると着飾り過ぎた愚かなイタリア風の気取り屋は「マカロニ」とばかにされた。 ロンドンでは、町の「マカロニ」たちが批判におじけることなく1760年にマカロニクラブを結成した。さらに、メンバーの風変わりな髪型からヒントを得た19世紀のイギリス人航海家たちは、カラフルなとさかのある南極の生き物に、マカロニペンギンというあだ名を付けた。 同様に、1775年のアメリカ革命期には、「マカロニ」がその髪型自体を指すようになり、地味で見当違いのヤンキー・ドゥードルは「帽子に羽根をさし「マカロニ」と呼んで気取る」のだった。
同じくらい興味深く難解なのが、「マカロニ」はアラビア語にルーツを持つ言葉であるという論だ。 「ドゥワイダ」(尺取虫)は、初期のチュニジア版バーミセリのアラビア名だが、ドゥワイダは麺が短いピースに分かれていて (21ページの補足記事参照)、 生麺の両端をくっつけると、「カラン」と呼ばれる小さな輪になる。アラビア語で「継ぎ合わせる」という意味の「カラナ」から来ている。 継ぎ合わせたものが、アラビア語の過去分詞を使って「マカルン」または「マクルナ」となる。 「マカロニ」からそれほどかけ離れていない。
フードライターのクリフォード・ライトは『地中海の饗宴』の中でこの論を慎重に引用しているが、食物史学者で料理本著者のナワール・ナスルッラーは 『エデンの園から最高の味: イラク料理の作り方と歴史』の中で率直にこう述べている。 「イラクでは(19)50年代まで、南部地域のパスタは「マカルナ」と呼ばれていた」。ナスルッラーは、バグダッドのようなコスモポリタン都市では、その言葉がすでに時代遅れであり、 代わって上品なイタリア風に「マカロニ」と呼ばれていた」と記している。
「マカルナ」と「イトリッヤ」はさておき、パスタは中東全土で多くの名前で知られていた。 アッカド語では「セミドゥ」とセモリナの関連性に加え、エール大学バビロニアン・コレクションの楔形文字粘土板で見つかった3700年前のバビロニアレシピ「脾臓のスープ」では、焼いた「カイアトゥ」(生地)を少量加えることになっている。 ナスルッラーは、この食材をこまかい細い麺と解釈できるのではないかとした。
「カイアトゥ」が派生したと思われるアッカド語の「カタヌ」 は、「細くこまかくなる」という意味だ」と彼女は説明している。 「アラビア語の「キタン」は、複数形が「カイアティーン」で、突き詰めると「糸」または「ひも」を表すアッカド語の「カタヌ」から派生した言葉である。 したがって、「カイアトゥ」の生地を薄くのばして「カタヌ」にした――すなわち糸かひも状に刻んだ可能性がある。」 鍋に入れる前に「カイアトゥ」を焼いたとあるが、これはパスタベースのスープやピラフの多くに使われるテクニックである。生地なら何でもいいというわけではなく、乾麺のような頑丈な生地が使われたことが示唆されている。
ナスルッラーによると、焼いた麺は今でもイラクの市場で売られている。 これらは「リシュタ」と呼ばれている。「糸」と訳されるペルシャ語だ。 「リシュタ」のレシピは13世紀以降アラビア語の料理本に登場し、ペルシャ語で「滑る」を意味する「ラクシャ」(麺)というそれまでの表現に代わって使われるようになった。 著名な食物史学者チャールズ・ペリーは、こうした用語の変化は、意味を明確にする目的でなされたと論じている。 「ラクシャ」は野生ロバのスープだけに使われる麺で、13世紀までに廃れてしまった可能性があるそうだ。 (言葉自体は他の言語や文化の中で残っていった。 今日、「ラクシャ」は中国・マレー系のスパイシーなスープのことで、オスマン帝国の一部または隣接した地域において、ハンガリーでは「ラクサ」、ロシアでは「ラプサ」、ウクライナでは「ロクシナ」、リトアニアでは「ラクスティニエ」、アフガニスタンでは「ラクチャク」、イディッシュ語では「ロクシェン」という言葉で残った。)
今は「レシュテ」と音訳されることの多い「リシュタ」は、「レシュテ・ポロウ」(そばめし)や「アーシュ・レシュテ」(麺入りスープ)など伝統的なペルシャ料理の多くで主役となる食材だ。 後者は「アーシュ・プシュテパ」(巡礼者のスープ)とも呼ばれ、愛する者がメッカへの巡礼に旅立つ前日や、または息子が家を巣立ち世に羽ばたく際に振舞われる伝統があった。
『ペルシャの伝説の料理』の著者マーガレット・シャイダによると、「麺が入った料理は、(人生の)手綱を持つとの意味を込めて従来から決断や変化の時に作られた」。 イスラム勢力の統治下に入る前のイランでは、麺入りスープは毎月初めに食べられていた。シャリダによると、今日のイラクでも残る習慣であり、毎月初めの祈りで振舞われる。 アーシュ・レシュテも宗教的な誓約を表す食べ物(ナズル)で、愛する者の長旅の安全や、子どもの病気の回復など家庭に関連した物事に神の介入を求めるものである。 「麺入りスープは、絡まった麺が人生のしがらみと似ていることから、誓約には特に適していた」とシャイダはみている。 |
だがギリシャ人とローマ人はデュラム小麦を使ってパスタを作ったのだろうか―― どちらとも言えない。ギリシャには「ラガノン」といって、粉と油で作った大きく平たい生地を焼いたり揚げたりしたものがある。 「ラガノン」はパスタの原型とされ、ローマ語の派生語「ラガヌム」と共に言及されることが多い。 紀元前4世紀のギリシャ詩人でゲラ(ジェーラ)のアルケストラトゥスは、地中海のグルメガイドとも言える『贅沢な生活』の中で、ラガノンに度々触れている。 ローマ時代には、アテナイオスが、知識人の夕食会を催すためのハウツー本『食卓の賢者たち』の中で、ラガノンのレシピを1世紀のギリシャ作家であるティアナのクリュシッポスから転用したと断言している。
ローマの料理人は、ラガヌムを切り、「ラガニ」あるいは「ラガナ」と呼ばれる「きれ」状にした。そして他の材料と重ねてオーブン皿に並べた。これが調理そして語彙上のラザニアの祖先だと思われる。 「ラガナと具材を交互にのせよ」と指示するのは、4世紀の『料理大全』だ。1世紀の伝説の美食研究家マルクス・ガビウス・アピシウスが伝えたレシピを編纂したものである。美食に人生を捧げたアピシウスは、贅沢なライフスタイルを維持するお金がなくなり命を絶ったと言われている。 アピシウスほど贅沢ではないが、長老カトー(紀元前234~149年)は、農場の管理と畜産に関する手引書『農学書』を著し、その中で「ファリナエ・シリグネアエ」(普通小麦)と「アリカエ・プリマエ」(セモリナ細粒)を混ぜあわせ、パイ生地の一種である「トラクタ」を成形するというチーズケーキのレシピを記録している。 その後紀元前68年から65年、ローマ詩人ホーレスは、フォーラムでの長い懇談を終えた一日の終わりに、深皿に盛りつけられたリークとひよこ豆と「ラガニ」の暖かい料理ほど落ち着くものはないと記している。
 |
| ニコラ・アルボン / Alamy |
| ギリシャの平たいパン「ラガノン」または「ラガナ」は、地中海北部のパスタ、そしてローマ人が具材と重ねて調理したラザニアの祖先かもしれない。 |
だがこれだけ詳しい情報があるにもかかわらず、デュラム小麦の生地を乾燥させたりゆでたりすることに触れた文献はなく、これらがパスタセッカでなかったことがわかる。 焼いたラガヌムはユダヤ人のマッツォのようなものだったと思われる。揚げたラガヌムは、フリッターやベニエに似ていただろう。 パスタ系の食べ物は、『古代ギリシャ世界の生態学』の著者ロバート・サラレスによると、「古典文献では、(パスタが)使われていないことが逆に目立つ」ようだ。 ここで疑問がわくだろう。 ギリシャ人もローマ人も創作力が高く、パスタが比較的単純なつくりであるにもかかわらず、なぜどちらも乾麺を作ろうと思わなかったのか。
一部の学者は、古代の製粉技術では、デュラム小麦をパスタに適した微粉に挽くことが困難であったと推測している。 また、古代の炭水化物の優先順位において、パスタはそれほど重要でなかったとする論もある。
「地中海地域では、古代から中世まで、粥とパンが穀物ベースの主食の代表格であった」と社会科学高等研究院のフランソワーズ・サバンは解説する。 彼女は夫のシルヴァノ・セルヴェンティと共に学術書『 パスタの歴史』を著した。 パンと粥の調理方法がそれぞれ独特であるため、この二つが交わることはなかったという。 パンはパスタのように生地をこねて作るが、パンは乾式加熱で調理する点でパスタと異なる。粥はパスタのように茹でて調理するが、穀物を粉ではなく全粒または粗挽きの状態で作る点でパスタと異なる。 「このことを踏まえると、パスタはどちらのカテゴリーにも通じるため問題外で、ゆえにどちらにも属さなかった」とサバンは記している。
西欧でこのような分類が最初に登場したのは、7世紀のセビリャのイシドールスの著作で、イシドールスは、ラガヌムを「茹でてから油で揚げる大きく平たいパン」と説明している。 例えると、「チョウミン」の付け合せの揚げ麺、または欧米の中華料理店で前菜として出される事が多いサクサクした揚げ麺のようなものだろう。
だが、古典文献にパスタの起源を東に求めるヒントがないわけではない。ホーレスの簡素な夕食風景には、語源の鍵が隠されている。
ホーレスは、ブーツの形をしたイタリア半島の「かかと」部分にあり、プグリアに隣接するギリシャの商業都市、ヴェヌシア(現在のヴェノーサ)の出身である。 ビザンチン族、ロンバルド族、ノルマン族、そして中世にはアラブ人の支配が繰り返されてきた地域である。 だがその間も、そして現在に至るまで、ホーレスが食した質素なひよこ豆、リーク、ラガニの料理は、この地域の名物として残った。この料理は「チーチェリ・エ・トリア」または「パスタ・エ・チェリ」として知られる。ひよこ豆(チェリ)と、タリアテッレの田舎版である太いひも状の「ラガネッレ」(当時の呼び名)で作った伝統料理だ。 ホーレスのラガニとラガネッレが語彙として明らかにつながっている(イタリア南部の言葉で「麺棒」を意味する「ラガナトゥーラ」は言うまでもなく)以外にも、「トリア」という言葉には地域性を表すさらに重要な意味がある。 「トリア」は、ケーキまたは薄い種なしパンを意味するギリシャ語の「イトリオン」から派生しているが、 15世紀には、そのラテン語の同語源語「イトリア」がまったく別のものを意味するようになった。
 |
| 『健康全書』 |
| 14世紀、ロンバルディの製本会社が、バグダッドのイブン・ブトランが作成した百科全書である11世紀の健康手引書に挿絵をつけたラテン語版を出版した。 これには「トリジ」と呼ばれるパスタのレシピが収められており、上のように女性が生地をこね、乾燥させている挿絵が付いている。 |
「祭日にバーミセリ(イトリア)を作る場合、それが乾燥させるためであれば、禁じられる。 鍋に入れる(直ちに調理する)ためであれば、許可される」――ユダヤ法について4世紀末から5世紀初めにかけて聖地で編纂された文書集である『エルサレム・タルムード』には、このように記されている。 その一節では茹でた生地を種なしパンと見なすかどうかが議論されているが、ここでの重要性は教義上の議論をはるかに超える。 これは、レヴァント地方の人々が生地を茹でていたこと、そして最も重要な点として、それを長い房にして乾燥させ保存していたことを示す最古の証拠である。「イトリア」と呼ばれたのはこの房だ。 「イトリア」はヘブライ語では「イトリオット」、アラビア語では「イトリッヤ」、イタリア南部では「トリア」として残り、すべて同じものを意味している。 パスタである。
“「トリア」はカラブリア、ナポリ、その他シチリア中央部の多くの町や村で用いられたパスタの呼び名である」と語るのは、『パスタとピザ』を著したシチリア生まれの人類学者フランコ・ラ・チェクラだ。 パレルモの、近所の静かなトラットリアで前菜サイズのピザをつまみながら、ラ・チェクラはこう語る。「誰がシチリアにパスタとその製造技術を伝えたか――シチリア人は迷わず答えるだろう。 アラブ人だよ。」
シチリアが次々と征服された9世紀に、国内の灌漑技術と農業技術の大半をアラブ人が開発したのだ」とチェクラは言う。 「その時アラブ人がパスタの作り方も伝えたというのが、シチリアの常識だ。」
チェクラの話には、伝説以上の意味がある。 初期のアラブ人医療ライターは、ギリシャやローマの先達と同じように、小麦の健康効果を認識していた。そして小麦の調理方法を議論する中でパスタにも触れている。 9世紀、医者であり辞書編纂家であったイシュ・バール・アリは、茹でたセモリナ生地を房にして乾燥させたものを「イトリッヤ」と呼んだ。 中世で有数の医学権威、エジプトのイシャク・イブン・スレイマンは、10世紀の著書『食品と養生の書』(欧米では『栄養学の書』として知られる)でパスタの調理方法を論じている。 さらに東に行くと、シルクロードの町、カザフスタン南部にあるオトラル出身の辞書編纂家アル・ジャワリ(10世紀後半)が、「イトリッヤ」を、小麦からできた「ヒブリヤ」または「毛状のもの」(「フレーク」の可能性もある)に似た食べ物だと定義している。
イタリアでのパスタとパスタづくりに最初に触れたのが、著名な中世アラブ人地理学者アル・イドリーシーにほかならない。 ノルマン人でアラブ好きなパトロン、ルッジェーロⅡ世のために1154年にまとめた『遠方への快適な旅の書』で、シチリア島北部にある沿岸の町を紹介しながら、アル・イドリーシーはパレルモの東30キロほどのところにある「トラビアという楽しい集落」に言及している。トラビアでは、「絶えぬ小川の流れが、たくさんのミルを回していた。 田舎の巨大な私有地では「イトリッヤ」が大量に作られ、別の場所へ輸出されている。 輸出先はカラブリア、そしてイスラム諸国、キリスト教諸国であった。 何隻もの船に積んで出荷された。」 (補足記事 The Last Pasta-Maker of Trabiaを参照)
 |
アル・イドリーシーが大きく取り上げたシチリア沿岸のトラビアは、地中海を見下ろす丘に佇む町。パレルモから車で1時間半ほどのところにある。 イドリーシーが書いた「巨大な私有地」はもうなく、何エーカーものデュラム小麦をセモリナに挽いたという製粉所もない。 前世紀中頃になくなったという最後の製粉所の跡地は、洗車場になっている。だがトラビアの大通りの中程にある不運なトラットリアの裏では、町最後の業務用パスタ職人が今も手打ちパスタを作っている。専門店級のアネリッティ、タリアテッレその他の人気パスタを、主に地元の顧客向けに提供する。
「パスタづくりは父から習いました」とオーナーのマッテオ・バルベラは語る。 「土曜日と日曜日にしか作りません。 粉と卵、水。 材料はそれだけです」。 粉はシチリアで唯一パスタ製造機でパスタを作るトマセッロから購入する。数マイル西のカステルダッチャで1910年に創業した企業だ。 だが粉さえもう地元産ではない。 アメリカとロシアからシチリア島に入ってくる。
だがバルベラは、トラビアのパスタの伝統を誇りに思っている。町の観光誌では特産品のシーフードやクラバップルのような西洋カリンと共に、パスタも取り上げられている。
「パスタ発祥の地で自分が最後のパスタ職人とはおかしな話です」と彼は語る。 「シチリア人ですが、アラブの最後の生き残りなのでしょうね。」彼は笑って言った。
 |
| トム・ヴェルデ |
| シチリア島トラビアにあるマッテオ・バルベラのカフェ。看板で宣伝されているのは持ち帰り用のパスタフレスカ(卵入りの生麺)で、家で調理する。 |
|
アル・イドリーシーの説明では、14世紀には産業の発展と貿易ネットワークが北に広がり、ジェノアを超えて拡大していったことが示唆されている。 パスタを明記した最古のイタリア語の記録は、1279年にジェノア兵士ポンツィオ・バストーネの遺言状として公証人が作成したもので、遺品目録には「マカロニが詰まった箱」と記されてあった。 これはパスタセッカに違いない。木箱で保存ができるのは乾麺しかないからだ。 13世紀のアンダルシアの作家イブン・ラジン・アル・トゥジビは、『食卓と最高の料理の歓び』で、イスラム世界西部で使われたさまざまなパスタを紹介している。その中に、乾麺が「ない」ときに使うパスタフレスカのレシピがあり、乾麺が市場で日常的に売られていた商品――つまり輸入品であったことがわかる。
パスタはその頃には詩人や権力者にも食べられていた。 トスカーナのジョヴァンニ・ボッカチオは、14世紀の名作寓意詩『デカメロン』で空想の風景をこのように描写する。「すりおろしたパルメザンチーズの山」の上に「マッケローニ とラビオリづくりしかしない人々」が住んでおり、「それらを雄鶏のスープで煮てから、山の下へと転がしていく。」
一方イングランド王リチャードII世の厨房では、料理長がボッカチオよりも現実的な方法でパスタを盛りつけた。もちろん定番のすりおろしチーズは外さなかった。 14世紀の王室料理本『料理の形態』(The Forme of Cury)を著した匿名のイギリス人は、「薄く伸ばした生地を刻み、沸騰したお湯の中に入れ、よく茹でる。 チーズをすりおろし、バターを塗り、「ロシンス」の上下に乗せて出す」と指示している。 「ロシンス」は要するにラザニアであった。レシピでは「ロシンス」の作り方として、デュラム小麦ではなくパン小麦を使うとしているが(したがってパスタフレスカだと思われる)、大事なステップとして、調理前に「硬く乾燥させる」としている。これはデュラム小麦でなければ不可能だ。
(「ロシンス」、すなわちラザニアを中世のアラビア語・ペルシャ語で言う「ラウジナジ」と関連付けようという学者もいる。「ラウジナジ」はアーモンドと砂糖、ローズウォーターで作られた薄いケーキで、硬質小麦と軟質小麦の両方を使う。 アラブ地域のお菓子の例にもれず、ケーキは菱型に切るのが一般的だ。 東洋学者のマキシム・ロダンソンは、こうした菓子と、同じような形をした紋章デザインを表すフランス語「ロズンジ」につながりを見出した。なお、英語の「ロゼンジ」(トローチ)は「ロズンジ」の派生語である。)
これらをはじめ、パスタに言及した中世ヨーロパの他の文献では、パスタは貴重で高価な商品で、地元では簡単に手に入らない輸入品であったことが示唆されている。
 |
| フラテッリ・アリナーリ写真博物館 / ブリッジマン・アート・ライブラリー |
| パスタを天日干しするこの絵は1900年のナポリの風景。パスタは「トリア」と呼ばれることが多かった。「トリア」は、レヴァント地方で5世紀以降知られていた長い房状の乾麺を意味する「イトリア」からきていると思われる。 |
「港と貿易に関連した製品であり、国内で作るようなものではなかった」とアルベルト・カパッティは述べる。 『食のイタリア文化史』を共著し、トリノの南にある食文化学大学で教鞭をとるカパッティは、 イタリア半島でのパスタ製造は、19世紀と産業革命の始まりまで普及していなかったと指摘する (イタリア北部のロンバルディで育ったカパッティは、食卓ではパスタでなくリゾット(米)が一般的であったと言う)。 それまでパスタの製造や消費といえばイタリア南部、という意識が一般的であった。 ナポリ、プグリアもそうだが、最も有名なのがシチリア島で、カパッティはイタリアのパスタ業界発祥の地である可能性が高いと見ている。
だがその祖先は、本当にアラブ生まれなのだろうか。 アル・イドリーシーがシチリア島で盛況であったパスタ業界に言及したのは、アラブ人の到来前に存在していたパスタ業界のことだろうか、それとも伝説のようにアサド・イブン・アル・フラットの戦艦と共に上陸したもののことだろうか。 最初期の料理本を紐解くと、ヒントが得られる。
アル・イドリーシー以前にイタリアの地でパスタセッカの言及がないように、アピシウスの時代から13世紀までヨーロッパには料理本に相当するものがなかった。 対照的にアラブ世界では、料理本が10世紀かおそらくそれ以前にアッバース朝バグダードで登場しているた。 「1400年前までは、世界のどの言語よりもアラビア語の料理本が多かった」と主張するのは、『中世イスラーム世界の料理』著者の食物史学者リリア・ザワリーだ。 料理本はどれも「料理の書」など、普通のタイトルがついているため、著者の名前と一緒に知られることが多かった。その点は今日の有名料理研究家の料理本と似ている。
知られる中で最も古いアラビア語の料理本で、初めてパスタに触れたのが、10世紀にアッバース朝の宮廷書記官サイヤール・アル・ワッラクがまとめたものだった。 この本では、カリフと宮廷役人が8世紀初めから9世紀にかけてまとめたレシピ集をもとに、パスタに関する章が設けられている。パスタはこの頃ペルシャ語で「滑る」を意味する言葉から、「ラクシャ」と呼ばれていた。 (補足記事『マカロニの語源』参照) また、ペルシャ帝国の君主ホスロー(579年没)の統治期間にパスタが考案された興味深い話も特徴的だ。
 |
「イタリアがあまりにも近いので、ピザの匂いがしてくる」とふざけるのは、チュジニアのガイド、ハテム・ボウリアルだ。 実際、イタリア半島とシチリア島は、チュニスはじめ北アフリカ沿岸諸国の港に近く、何世紀にもわたって文化交流が行われてきた。パスタなど食文化の交流も例外でない。 ローマにある国際パスタ機関によると、チュニジアは実際にパスタ製品の消費で、イタリアとベネズエラに次いで世界3位である。
 |
| シンディ・ホプキンス / Alamy |
「この統計は驚くほどのことではありません。チュジニア人はほとんど毎日パスタを食べていますから。 広く愛されています」と語るのは、『チュニジアのイタリア人:コミュニティの物語』の著者 マリネッテ・ペンドラだ。 彼女によると、チュニジアには10世紀ごろからイタリア人が住んでいる。 19世紀末から20世紀初めは、ファシズムと戦争、貧困を逃れるために多くのイタリア人が南へ逃げ、都市部各地でコミュニティーを形成した。
パスタを好んだイタリア人移民は、同じように各種パスタ料理を好んだ北アフリカのアラブ人と意気投合した。徹底的なリサーチをもとに執筆した『地中海の饗宴』では、フードライターのクリフォード・ライトがこれらの料理をリストしている。 そのうち今でも人気があるのを紹介したい。
リシュタ: 卵入りのフェットチーネで、豆や野菜と合わせることが多く、前菜やスープとして振舞われる(リシュタ・ジャリッヤ)。 シリアとレバノンではレンズ豆も使われる。
ドゥワイダ: チュニジア・アラビア語のチュニジア方言で、2.5センチ程度のピースに分かれたバーミセリのこと。 合わせて小さな輪にすると、シチリア名物の「アネリッティ」と同じになる。文化交流が行われたことが大いに示唆されている。
ハラリム、トリトル、カタ: 小さな粒状のスープパスタで大きは様々。クスクスのように蒸して調理することもある。
ムハマス: クスクスの一種として分類されることもあるこの小さな丸いパスタの名前には、「小さなひよこ豆」を意味する「フマイス」から派生したアラビア語の「ハムス」(ひよこ豆のディップ)が含まれている。だが実際のムハマスはポップコーン大である。 焼いたムハマスの粒は、アメリカで「モグレビーヤ」として売られている。マグレブ、つまり北アフリカにルーツがあることを反映した名前だ。
エデオイダ: バーミセリの一種で、遊牧民族であったアルジェリアのサハラ砂漠の戦士が使ったパスタ。「タリア」(イタリアの略)とも呼ばれた。 |
話はこうである。寒い日に狩りに出かけたホスローは、料理人に温かい野生のロバのスープを作るように命じる。 だが王は後からの思いつきで、スープに「生地の破片」を入れて作ることを提案した。 喜んだ王は、「おいしくてその後3日続けてその料理だけを食べた」。 この説はもちろん伝説だが、アル・ワラクの本には、実用できるパスタレシピが収められている。 この中のナバテア風チキンは、鍋に「イトリヤ3つかみ」を入れ、火が通るまで煮るとしている。この作業は明らかにパスタセッカのことだろう。 初期のアラブパスタは小さく、13世紀のスペイン系ムスリムの料理本で説明されているように、「コリアンダーシード」のような粒状または米粒状だった可能性も高い。
「穀物の粒をまねて作られ、主にスープで用いた」とサバンは述べ、この形状はまた、詰め込んだときに無駄なスペースができず携帯に適していたと指摘している。
中世全般を通じて、ヨーロッパの学者はアラビア語の文書を翻訳する中で、上記をはじめ栄養学や料理に関する多くの本に出会ってきた。 その一つに、バグダッドから来た11世紀のキリスト教徒医師イブン・ブトランの『健康全書』(タクイム・アル・シハ)がある。 この本は、パレルモのシチリア王マンフレッド(1258~1266年在位)の宮廷でラテン語に訳された。その後14世紀になって、挿絵がふんだんに盛り込まれたラテン語版『健康全書』(タクヌム・サニタティス)がロンバルディで出版された。 収められたレシピの中には、「トリジ」またはパスタがあり、女性2人がパスタを作る詳しい挿絵がついていた。女性は生地をこね、長いひも状になったものをラックで乾かしている。20世紀初頭までほぼ変わらずに残った手法である (イラストはこちら)。
アラブ料理は、とくにイタリア料理を題材とした最古のヨーロッパ語文書である13世紀終わりの『料理の書』にも、独特の風味をもたらした。 この本にはラザニアの他にも、アラビア語から派生した名前やレシピがいくつか収められている。匿名の著者がアラビア語の文書からレシピを転写していた可能性もある。 例えば、「ロマニア」(チキンとザクロの「ルンマニヤ」より)、「スマチア」(チキンとウルシ、アーモンドの「スンマキヤ」より)、「リモニア」(肉とレモンの「レイムニヤ」より)といったレシピがあった。
15世紀、パスタの詳しいレシピと下ごしらえの記述が、マエストロ・マルティーノ・コモの『料理芸術の書』に登場する。コモはバチカンの司書で仲間のルネッサンス・ヒューマニスト、バルトロメオ・サッチから「料理王子」と呼ばれていた。 だが最初の現代版イタリア料理本とされるこの本でも、長くひも状に切ったパスタは「トリティ」(トリアなど)と称されていた。著者は、パスタのアラブ起源を間接的に認めたことになる。 また、レシピの一つに「シチリア風マカロニ」があるが、材料に、小麦粉、卵白、そして欧米では珍しいが高級アラブ・ペエルシャ料理では一般的なローズウォーターを用いる。 高価で香りの強いローズウォーターが使われたということが、パスタセッカの価値を裏付けている。 ローズウォーターは、村よりも王室の厨房に登場することが多いからだ。 マルティーノは、生地を、「手のひらの長さで、藁ほどの細さ」の細長いひも状に切るよう読者に指示している。そして空気が温かく乾燥した「8月の月光」での保存処理を指示している。
自家製パスタと言えば聞こえはいいが、ルネッサンス期によくある調理法はひどいものだった。 マルティーノのレシピの最後にこう書かれている。「マカロニは2時間茹でなければならない」(バルトロメオ・サッチはこれに異議を唱えている。 1475年に出版された世界初の印刷版料理本で、幅広い人気を博した彼の『尊敬すべき喜びと健康』では、パスタによっては 「我らの父よ...」 と3回言うくらいの茹で時間で十分だとしている。「歯ごたえ」を意味するアルデンテのパスタが初期のイタリア料理でも好まれたことがわかる。
「マルティーノは、パスタを茹で過ぎるイギリスやドイツのやり方は間違いではないが、昔のやり方だと言う」とアンドレア・ガグネシは笑って言った。ガグネシは、イタリアの料理本を執筆し自ら料理も教えるロレンザ・デ・メディチが設立したトスカーナのバディア・ア・コルティブオーノで料理学校のシェフをしている。 ガグネシによると、マルティーノのアイディアにはもう一つ傑作がある。茹でたパスタをフォークで食べるというものだ。素手では熱くて食べられないから、という理由なのだそうだ。
 |
| ロベルト・ランダウ / Alamy |
| 1970年代ロサンゼルスの沿道の看板。最も一般的な現代パスタの姿―― セロファンに包まれたファミリーサイズのスパゲッティが描かれている。 |
ウェルダンかアルデンテか、好みはさておき、現代のイタリア料理愛好家なら、中東起源説を学ぶよりも実際に食べたほうが飲み込みが早いだろう。 だが、アラブ世界の人々が、パスタとパスタ製造技術を西欧に普及させるうえで大事な役割を果たしたことを示す重要な証拠はある。 この証拠は、前述の3つの問いに対する答えにもなる。 パスタに欠かせないデュラム小麦は、メソポタミアからシリア、エジプト、北アフリカ、イスラム支配下のシチリアまでアラブ世界全土に存在した一般的な穀物である。 アラビア語の料理本は、セモリナ粉の生地を乾燥させ、保存が効く形体にしたことを記した最初の文献で、 さらにこれを茹でて調理することに最初に触れたのが、エルサレムで書かれた学者の文書である。
今日イタリアと切っても切り離せないパスタが、イタリアの土地から離れた場所に起源があるとはどういうことか。 一部の食物史学者は、最初のパスタは砂漠に住むアラブ遊牧民が考案したとしている。なぜなら彼らは携帯性に優れた食料に頼っていたためである。 一方、デュラム小麦が定期的に手に入ること、それを挽くための道具を持っていることは、遊牧民の能力では不可能だとして、この仮定に懐疑的な学者もいる。 フードライターのクリフォード・ライトは、妥協案を提案している。 パスタセッカは、北アフリカを横断する中世アラブ軍と共に伝来した、というものだ。 結局のところ、パスタセッカは便利で腹持ちのいい食料であったし、ラクダに乗せて運ぶのにもちょうど良かった。あるいは船の船倉に保管しやすかったというのも説得力がある。そのいくつかが約12世紀前にシチリア島の沿岸に錨を下ろしたのかもしれない。

|
 |
|
風味だけでなく色のアクセントとして好まれる香辛料のパプリカは、乾燥したパプリカや唐辛子を粉末にしてできたものだ。 パプリカと唐辛子は、オスマン帝国時代にヨーロッパと中東に伝わった。 使う品種と、種を加えるか加えないかによって、パプリカパウダーは辛味の少ないものから甘いもの、涙や鼻水が出るほど辛いものまで刺激の幅も広い。 ここで紹介するレシピに辛いものはお勧めしないが、もし使う場合はそのように明記するか材料に「唐辛子」と記載してある。 パプリカが多用されるが驚くなかれ。 大さじ4で間違いはない。 分量は4~6人分。
- オリーブオイル 1/3カップ+盛り付け皿に塗る分として少量
- 玉ねぎ 3つ(半分に切ってから厚めにスライスしておく)
- ニンニク 3かけ(潰して皮を剥いておく)
- 塩
- パプリカパウダー 大さじ4
- クミン 小さじ1
- カットトマト缶 2カップ(細かく切ってあるもの、ジュースも使う)またはつぶしたトマト2カップ
- フェットチーネまたはタリアテッレ 350グラム
- プレーンヨーグルト 1カップ(室温に戻す)
大きめのフライパンに油をひき、玉ねぎとニンニクを炒め、塩を振る。蓋をして弱火で5分間煮る。 蓋をとり、玉ねぎが柔らかいが歯ごたえがある程度まで弱火で炒める。 玉ねぎが茶色やあめ色にならないように注意する。 火を弱め、パプリカパウダーとクミンを素早く混ぜる。 1分ほど炒めて風味をつける。 極弱火のまま、パプリカパウダーが苦くならないように、手を休めずにかきまぜる。 トマトを加え、塩で味を整え、10分間煮る。
盛り付け皿に油を塗って表面をコーティングする。 ヨーグルトを泡立て器でかくはんし、塩をひとつまみ入れる。 沸騰したお湯に塩を加え、パスタを茹でる。 柔らかくなったらお湯を切り、皿に盛る。その上に炒めた玉ねぎをかける。 ヨーグルトをのせるか、別の容器に入れて出す。
|

|
 |
アラブの料理人はその昔、茄子は苦いと嫌っていた。 だが10世紀にはイブン・サッヤール・アル・ワラクの料理本に記載された方法にならい、下ごしらえの段階で茄子に塩を振り、苦味を取り除くようになった。 ここでは、イタリア南部の自然の恵み(パプリカ、トマト、アンチョビ)と、アラブ人が伝えた料理テクニック( 茄子とスパイス、とくに甘みとこくの組み合わせ)が満載のレシピを紹介する。 分量は6~8人分。
- 茄子 中2本(洗って余分な皮を取り除く)
- オリーブオイル 1/2カップ+大さじ3
- ニンニク 大3かけ(みじん切り)
- 塩
- 皮を剥いて刻んだトマト 900g(または缶入りプラムトマト800g。ザルにあけ刻む)
- 黄色または赤のパプリカ 2個(2.5センチのさいの目切り)
- 唐辛子フレーク 小さじ1/4~1/2
- シナモン 小さじ1
- アンチョビのフィレ 6~8(塩漬の場合は洗って塩を落とす。みじん切り)
- レーズン 1/2カップ
- ケイパー 大さじ1(水ですすぐ)
- バーミセリ 450g
茄子を1センチ強のさいの目に切り、ザルに層にして重ねる。各層に塩をふる。 皿とおもりをその上にのせて、1時間水抜きをする。 水ですすぎ、ペーパータールでやさしく絞って乾かす。
大きめのフライパンにオイル1/2カップとニンニクを入れ、ニンニクが半透明になるまで弱火で炒める。 フライパンに茄子を加え、中火~強火できつね色になるまで炒める。 残りのオイルをフライパンに入れ、トマトとパプリカを入れて混ぜる。 塩、唐辛子、シナモンを軽く振って味を整え、蓋をして15分間煮る。
アンチョビ、ケイパー、レーズンを加えて混ぜ、蓋をしてさらに15分間煮る。
大きな鍋にお湯を沸かし、塩を入れたらバーミセリを茹でる。柔らかくなったらお湯を切り、フライパンの野菜と合わせる。 |

|
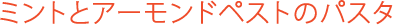 |
「ペスト・ジェノベーゼ」を知っている人は多いと思うが、イタリアでは他にも各地で伝統的なペストのレシピがあることはあまり知られていない。 「ペスト・トラパネーゼ」は、シチリア島西部のトラパニ港の伝統レシピ。ジェノベーゼのように松の実は使わず、アラブ風にアーモンドを使う。 昔ながらのトラパネーゼのレシピではバジルとトマトが使われるが、ここではミントと香菜を使ったアラブ風の現代バージョンを紹介したい。 分量は4~6人分。
- ソース
- ミントの葉 1カップ(詰め込んだ状態で)
- イタリアンパセリ 1/2カップ(茎を取りカップに詰め込んだ状態で)
- 香草の葉 1/4カップ(詰め込んだ状態で)
- 湯むきした無塩アーモンド 1/2カップ
- ニンニク 大2かけ(皮を剥いて半分に切り、中の青い部分を取り除く)
- コリアンダーパウダー 小さじ1
- 塩
- レモンジュース 小さじ2
- オリーブオイル 1/2カップ
- バーミセリまたは細いスパゲッティ(スパゲッティーニ) 350g
- トッピング
- オリーブオイル 大さじ1
- 刻んだミントの葉 1/4カップ
- レーズン 1/4カップ
- アーモンドスライス 1/4カップ
- バター 大さじ3(室温に戻す)
ミントとパセリを洗い、水気をしっかりとる。 フードプロセッサーかミキサーにかけ、ハーブ類が細かくなるまで回す。 さらにアーモンド、ニンニク、コリアンダー、塩を加え、アーモンドとハーブ類が細かくなるまで回す。 フードプロセッサーを一定の速度で回した状態で、投入口からオリーブオイルを注ぎ、均等に混ざるようにする。 レモンジュースを加える。 できたソースを温めた盛り付け用のボウルに移す。
小さいフライパンにオリーブオイルをひき、熱いうちにミント、アーモンド、レーズンを入れて合わせる。 アーモンドが軽いきつね色になり、レーズンが膨らむまで手を止めずに混ぜながら和える。 火から下ろし、すぐにバターに回し入れ、バターが溶けるようにする。
沸騰したお湯に塩を加え、柔らかくなるまでパスタを茹でる。 お湯を切る前に、大さじ3杯分の茹で汁を取り、ソースに入れて混ぜる。 お湯を切り、盛り付け用のボウルにパスタを移す。 トッピングをかける。 |

|
 |
フリーランス・ライターの トム・ヴェルデ は『サウジアラムコ・ワールド』でも多くの記事を手がけている。イスラム研究およびキリスト教徒・イスラム教徒の関係を専攻し修士号を取得。 長年にわたり、トムと姉のナンシー・ヴェルデ・バーは、自家製パスタディナーだけでなく、多くの著作プロジェクトを共に手がけた。 |
 |
料理ライター、ナンシー・ヴェルデ・バー はこれまで数多くの本を執筆してきた。受賞作3作を含む著作歴には、 We Called It Macaroni (Knopf, 1991)、In Julia’s Kitchen with Master Chefs(ジュリア・チャイルド共著、Knopf, 1995)、Make It Italian (Knopf, 2002)がある。 バーは、『Gourmet, Food and Wine, Bon Appétit, Cook’s Magazine』と『Fine Cooking』では多くの記事を出版した。 トム・ヴェルデの姉である。 |
翻訳記事に関するご意見ご要望
翻訳記事についてお気づきの点がありましたら、saworld@aramcoservices.comまでご連絡ください。今後の改善に役立てさせていただきます。ご送信の際は、件名を英語で “Translations feedback” としてください。多数のコメントをいただく場合、すべてのメールに返信できない可能性もありますので予めご了承ください。
--編集部 |