 |
| JWMプロダクションによる提供 |
| 2,500人のユダヤ人を助けてナチの国外追放を逃れることができるようにしたアルバニアのムスリム、米国を拠点とする写真家のノーマン・ガーシュマン(Norman Gershman)が撮影したそれらアルバニア人とその子孫の写真。これらを元に映画「約束(The Promise)」は作成された。 ガーシュマン氏は、「この小さな国、そして彼らが行ったことから、世界は学ぶべきものあります」と語る。 |
両方とも、魅力的で、サスペンスに満ちた感動的な話を取り上げると同時に、予想外の忘れられないヒーローに関する実際に知られていない歴史を記録することで、社会に貢献することになった。
「ライヒの敵:ヌーア・イナヤット・カーンの物語(Enemy of the Reich: The Noor Inayat Khan Story)」は、ナチ占領下のパリで活動する英国スパイであったインド系アメリカ人の女性イスラム教徒の物語を追ったドキュメンタリードラマである。彼女は、最もあり得なさそうな、しかし最も能力のあるスパイであった。 「約束(Besa: The Promise)」は、困っている人がいたら見知らぬ人であっても守る、という昔ながらの行動規範に従って、少なくとも2,500人のユダヤ人を保護した多くのアルバニア人に関する物語のドキュメンタリーである。
これらの映画の登場人物は、非常に異なる背景を持っており、映画のスタイルも異なっているが、いずれの映画も、第二次世界大戦中のムスリムの英雄たちを描写する新しい道を開拓することとなった。
 |
| ユニティ・プロダクション・ファンデーションによる提供 |
| 「ライヒの敵」では、グレース・スリニバサン(Grace Srinivasan)がヌーア・イナヤット・カーン役を演じた。カーンは、英国の無線送信器を秘書のタイプライターケースに偽装させ、ナチ占領下のパリで約4ヶ月間活動した。毎日移動することさえあった。 |
ホロコーストは、主にキリスト教徒が多いヨーロッパで行われたため、ナチとその同盟国が北アフリカおよびイスラム教徒の多いバルカン地域にまで侵略を進めたこと、そしてそれらの地域に住む人々も抵抗、救出を行ったことは忘れられていることが多い。
歴史家でワシントン近東政策研究所(Washington Institute on Near East Policy)のエグゼクティブディレクターであるロバート・サトロフ(Robert Satloff)は、2007年に出版された自著「義人の中で:アラブ世界にまで及んだホロコーストにおける失われた話(Among the Righteous: Lost Stories from the Holocaust’s Long Reach into Arab Lands)」の中で、「アラブ世界、そして迫害が起こったすべての地域におけるユダヤ人に対するナチ、ビシー、およびファシストの迫害のすべての段階において、アラブ人はユダヤ人を助けた」と書いている。同書は、この題材を扱った数少ない歴史回顧録である。 サトロフ氏は、ナチに占領されたアラブ世界におけるアラブ人による協力や支援の割合は、ナチ占領下のヨーロッパ人による割合とほぼ同じであるが、アラビア人やイスラム教徒の多くは迫害に強烈に反対し、ユダヤ人と和平を結ぶ公式の立場を表明した。一方、他の人々は迫害の片棒をかつぐことになる支援を打ち切るにとどめていた。 同氏は、「アラブ人の中にはユダヤ人と同じ運命をたどったものもおり、その経験を通じて、仲間に対する独特の絆が育まれていった。 そして、アラブ人がユダヤ人に対して精神的支援以上のものを提供することを選ぶこともあった。 自身の命も危険にさらされる中で、勇敢にもユダヤ人の命を救ったのだ」と書いている。
「ライヒの敵」のルーツは、ユニティ・プロダクション・ファンデーション(Unity Productions Foundation、UPF)の創設者およびプロデューサーであるアレックス・クロンマー(Alex Kronemer)およびマイケル・ウルフ(Michael Wolfe)にある。2人は、2010年のほぼ同じ週に、フランスに住む別のホロコースト生存者から連絡を受けた。どちらの人もイスラム教徒にいかに助けられたかを語った。 この話に両プロデューサーは啓発を受けた。どちらも第二次世界大戦中のイスラム教徒のヒーローなど聞いたこともなかったからだ。
クロンマー氏は、「そのような短期間に私たち2人がこのような話を聞いたことで、宇宙が私たちに語り掛けているように感じました。それでもっとよく調べよう、ということになったのです」と語る。
ほどなくして、彼らはもっと多くの話について知ることとなった。 例えば、インド人およびアルジェリア人のイスラム兵士は、それぞれ英国およびフランスのためにヨーロッパで戦った。一方で、フランスのボビニーにあるフランス・ムスリム・イブン・スィーナー病院(Franco-Muslim Avicenna Hospital)の医師らは、米国人や他の連合軍兵士の治療にあたった。 フランス人のキャバレー歌手であるシモン・ハラリ(Simon Halali)は、パリのグランド・モスクで助けを受けた多くのユダヤ人の1人だ。イスラム教徒は、書類を偽造して、彼の名をサリム(Salim)に変えイスラム教徒であるように見えるようにした。この話は、2012年のフランス映画「レ・ゾム・リーヴル(Les Hommes Libres、「自由人」の意、フランス語のみ)」に取り上げられている。
映画製作者らは、複数のストーリーを組み合わせ、強力なドキュメンタリーとすることもできただろうが、ヌーア・イナヤット・カーンの話に一本化することにした。彼女の深い霊性、そして女性としての立場が興味深いものであったためだ。
クロンマー氏は、「彼女が人を感動させるのは、彼女が包含的な人間らしさをもっていたためです。 ナチのイディオロギーは、彼女が信じるすべてのものに敵対しており、彼女は傍観者的立場を取ることができなかったのです」と語る。
「ライヒの敵」は、ほとんどの撮影がボルチモアおよびワシントンD.C.で行われ、地元の演劇業界の俳優らがキャスティングされた。このカーンのストーリーには、学者や親族からの話がちりばめられている。 アカデミー賞受賞歴のある女優、ヘレン・ミレン(Helen Mirren)がナレーションを行っている。
カーン役を演じたグレース・スリニバサンは、「カーンは本当に強い女性で、勇敢さや度胸を見せつけましたが、非常に変わった環境で育った若い女性であったことも事実です。私は、このカーンを表現してみたいと思いました。 彼女は、私と同様にインド人と米国人の間に生まれました。自分と同じ境遇の人の話を聞くことは今までほとんどありませんでした。 彼女の話は語り継がれてしかるべきであり、私はその一端を担えることに興奮しています」と語る。
 |
| JWMプロダクションによる提供 |
| レジェプ・ホッジャ(Rexhep Hoxha)は、困っている見知らぬ人を保護するというアルバニア人のベサ、つまり約束に従って、彼の父親がアラジェム(Aladjem)一家をかくまった時、17歳であった。 映画の中で、彼はアラジェム家の故郷であったブルガリアのビディムにある廃れた礼拝堂を訪れる。 |
カーンの父親、ハズラット・イナヤット・カーン(Hazrat Inayat Khan)は、インド出身のイスラム神秘主義(スーフィー)の伝道師・音楽家で、第一次世界大戦後に、伝道および教育のためにアメリカに渡った。 そこで、彼はアルバカーキ生まれのオラ・ベイカー(Ora Baker)と知り合う。 彼らは結婚してモスクワに移り住み、1914年にヌーアが生まれる。 その後まもなく、一家はロンドンに、そしてパリに移り住む。一家は、裕福な後援者からパリ郊外に別荘を買い与えられる。その別荘は、「ファザル・マンジル」、つまり「祝福の家」として知られるようになった。 訪問者が彼女の父親の話を聞くためにやってきて、若いヌーアはその話にどっぷり浸った。彼女は、それが最も牧歌的な時間、そして人生の中心となる場所だったと描写している。 しかし、彼女の父親が突然亡くなり、この時間は悲劇的な終わりを告げた。 ヌーアの母親は、悲しみで体を動かせなくなり、母親の代わりにヌーアが小さな兄弟たちの面倒を見ることになった。
彼女はソルボンヌ(パリ大学)での学業を続け、後に子供向け作家として成功した。彼女は子供向け雑誌、および短編物語集などの出版を行った。 1940年、ナチのフランス侵攻に先立って、カーンと彼女の家族は英国に逃れた。
ここで彼女は、無線通信士として英空軍婦人補助部隊に入隊する。 フランスでの任務を果たした後、ウィンストン・チャーチル(Winston Churchill)により設置された秘密部隊である英軍特殊作戦部(SOE)に採用され、敵陣に潜んで地元のレジスタンス戦士らを支援する任務を受けた。
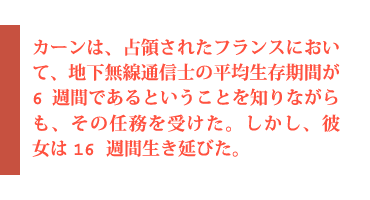 英国の訓練記録では、カーンが理想主義者であり、上司らはそれをマイナス点とみなしていたことが記されている。 例えば、彼女はうそをつくことを拒否した。 ドキュメンタリーは、それらの否定的な報告は彼女の浅黒い肌とイスラム教徒としての信仰に対する偏見の結果であった可能性を示唆している。 しかし彼女の無線技術は非常に素晴らしく、フランスではSOEの無線通信士が切実に必要とされていた。というのも、ナチの追跡トラックが冷酷なほど簡単に無線通信士らを暴いていっていたのだ。 この任務の平均生存期間は6週間だった。
英国の訓練記録では、カーンが理想主義者であり、上司らはそれをマイナス点とみなしていたことが記されている。 例えば、彼女はうそをつくことを拒否した。 ドキュメンタリーは、それらの否定的な報告は彼女の浅黒い肌とイスラム教徒としての信仰に対する偏見の結果であった可能性を示唆している。 しかし彼女の無線技術は非常に素晴らしく、フランスではSOEの無線通信士が切実に必要とされていた。というのも、ナチの追跡トラックが冷酷なほど簡単に無線通信士らを暴いていっていたのだ。 この任務の平均生存期間は6週間だった。
1943年、カーンは人里離れた田舎の滑走路に降り立ち、パリに潜り込んだ。秘書のタイプライターのように見えるケースに入れて無線を持ち込んだ。 彼女の任務は、ロンドンと地元のスパイの間の通信を行い、地下活動を続けるレジスタンスのネットワーク、プロスパー(Prosper)を支援することだった。 しかし、ほどなくしてプロスパーは裏切りにあい、工作員のほとんどが逮捕された。 カーンは、頻繁に場所を移動しながら16週間追手から逃れた。その間、ゲシュタポの無線探知器による追跡を受けながらも、ロンドンにメッセージを送り続けた。 1943年10月、彼女は逮捕・投獄されると、ドイツのダッハウ(Dachau)強制収容所に収監され、1944年9月に処刑された。
スリニバサン氏は、「私は、ヌーアの人生の光と影のバランスを取るのが非常に難しく感じました。 彼女はファンタジーや空想、詩や芸術を愛し、子供時代はこの空想の世界で生きていたといっても過言ではありません。 彼女の人生のこの部分は、そこで恐らく死ぬことを知りながらもフランスに潜入し、恐ろしい状況下でもあきらめなかったということから導き出される強靭な人物像とは、全く異なっているのです。 幾重にも層が重なったような彼女の魂を表現する方法を探ることは、とても興味深い経験であり、ドキュメンタリーでは彼女のファンタジックな部分と実利的部分の両方に光を当てています」と語る。
ベサという言葉は、直訳すると「約束」という言葉だが、その意味はもっと深いものである。この言葉に動かされ、米国を拠点とする写真家であるノーマン・ガーシュマンは、第二次世界大戦中にユダヤ人を保護したアルバニア人の記録を残したいと願うようになった。 2002年、彼は初めてアルバニアを訪れた。今日、アルバニアでは70%がイスラム教徒、30%がキリスト教徒という割合になっている。彼はそこで知った事実に驚愕した。傍観者の海におけるほんの一握りの例外的な人々ではなく、ベサと呼ばれる伝統的な行動規範に従って、国全体としてユダヤ人を救うために尽力したというのだ。ベサでは、困っていて助けを求めるのがたとえ見知らぬ人であっても、救助の手を差し伸べることを教えている。
ガーシュマン氏が撮影した写真を友人のジェイソン・ウィリアムス(Jason Williams)に見せると、二人は映画を作るしかない、という意見で一致した。ウィリアムス氏は映画プロデューサーで、JWMプロダクションの創設者、文化的プログラミングのスペシャリストでもある。
ウィリアムス氏は、「この映画は、ホロコーストが起こったことのイスラム教徒による証拠を提供し、それと同時に、当時の脅威に向かって正しい行動をとったイスラム教徒に関するストーリーを明らかにしています。ほとんどのキリスト教徒はそうしなかったのにです」と述べる。
映画の中でガーシュマン氏は、「この小さな国、そして彼らが行ったことから、世界は学ぶべきものあります」と語る。 実際アルバニアは、第二次世界大戦後、大戦前と比較してユダヤ人の数が増えた唯一の国となっている。
 |
| ユニティ・プロダクション・ファンデーションによる提供 |
| フランス語が流暢で、敬虔なイスラム教徒の一家で平和主義者として育てられたカーンは、英空軍婦人補助部隊に入隊後、無線の技術を習得した。 占領されたパリの地下に潜る無線通信士として、彼女は英国とフランス・レジスタンスの唯一のつながりとなっていた。 |
しかし、ドキュメンタリーには過去を振り返る以上の意味がある。 サスペンスに満ちた謎、そして現在も展開する追求を密接に結びつけている。 レジェプ・ホッジャの父親で、「貧しい中で生まれ貧しい中で亡くなった」ペストリー職人であったリファト(Rifat)が、ニッシム(Nissim)・アラジェムおよびサラ(Sarah)・アラジェム、12歳の息子アロン(Aron)のユダヤ人一家が、1943年の祝日のある日、彼の店に訪れて助けを求めたいきさつについてレジェプに初めて語ったのは、彼が17歳の時であった。 アラジェム家は、枢軸国と同盟を結び、数々の反ユダヤ人的法律を執行したブルガリアから逃れていた。当時のアルバニアは、イタリアに占領されていた。イタリアもナチスドイツと同盟を結ぶ枢軸国であったが、ユダヤ人に対してある程度の自由を認めていた。 リファトをすぐに店を閉め、アラジェム家を自宅に招くと、家族に部屋を提供した。
数か月後、ナチはアルバニアにも侵攻し、アラジェム一家の命は大きな危険にさらされることとなった。 1944年、アラジェム一家はアルバニアから逃げることにしたが、ニッシムは、その時すでに親密な親友となっていたリファトに、家宝であった3冊の祈祷書を託し、アルバニアが自由になったら取りに戻ると告げた。
しかし、戦争が終わっても、アルバニアは強力な共産主義政権下にあり、世界で最も閉ざされた国となった。 1990年に共産主義政権が崩壊して初めて、レジェプは祈祷書を本当の持ち主に返したいという父の願いを実現させる機会を得た。70年以上の時を経て、この2つの家族はまた一つになったのだ。
ユダヤ人を助けたアルバニア人は、貧しい農民からアルバニアの国王、ゾグ1世(Zog Ⅰ)まで様々な背景の人々におよぶ。ゾグ1世は、ヨーロッパ唯一のイスラム教徒の国王で、1939年、アルバニアへの入国を希望するユダヤ人に対して国境を開き、少なくとも400人分のパスポート、そして数えきれないビザを発行した。 この中には、ハンブルグからやってきたヨハンナ・ノイマン(Johanna Neumann)の一家がいる。
一家は、初めはアドリア海に面する湾岸都市ドゥラスの郊外で農民一家と住んでいたが、ナチが侵攻してからは、ドイツで教育を受けドイツ語が堪能で、ドイツ人の妻がいたアルバニア人の技師、ニャジ・ピルク(Njazi Pilku)の一家のもとに移り住んだ。 ナチが戸口にやってきて、ノイマン一家が誰なのか詰問されると、ピルク一家は彼らがドイツからやってきたいとこであると答えるのだった。
現在、ワシントンD.C.の米国国立ホロコースト記念博物館で基金アソシエートとして働くノイマン氏は、「もてなし、暖かさ、これらは本当に素晴らしいものです。助けてくれた家族は、自分たちも危険にさらされました。 彼らが私たちをかくまっていることがナチに知れたら、その場で皆殺しだったのです」と語る。
 |
| ユニティ・プロダクション・ファンデーションによる提供 |
| 二重スパイに裏切られ、彼女は1年以上収容所で過ごし、その後ダッハウ強制収容所で処刑された。 |
エルサレムにあるヤド・ヴァシェム・ホロコースト記念館には、「諸国民の中の正義の人」、つまりホロコーストの際にユダヤ人を助けた非ユダヤ人を称える名誉の壁がある。ピルク家の勇気に敬意を示し、1992年、ノイマン氏はニャジ・ピルクを名誉の壁に含めるよう推薦した。 ニャジ・ピルクは、ここに称えられている69人のアルバニア人の中の1人だ。
アルバニア人は、アルバニアを占領していたイタリア人も保護した。イタリアは連合国軍に降伏した後、ナチスドイツのターゲットとなっていた。 ノイマン氏は、ロマ(ジプシー)もアルバニアに住んでおり、それらジプシーたちも保護された、と語っている。 彼女は、「私が知る限り、彼らは退去させられませんでした」と語る。
ウィリアムス氏は、「私たちのこのタイミングは、まさに好運でした」と語る。ドキュメンタリーでインタビューした救助された、または救助した24人のうち少なくとも18人がその後亡くなっているという。 「ですから、この仕事は非常に重要だったのです。 もし私たちがこの映画を製作しなければ、この記録も存在しなかったのです。 歴史も存在しないことになってしまいます。 この真実は、誰にも知られることなく終わっていたかもしれないのです」と説明を続ける。
ホッジャ氏も、失われてしまうかもしれない、そしてすでに失われてしまった数々のストーリーについて危惧している。
彼は電子メールを寄せ、「ユダヤ人を助けた人の多くはすでに亡くなっています。 もちろん、多くのストーリーが一度も日の目を見ることなく終わります。 私自身は、自分の父親からより、映画製作者の方々からたくさんのことを学びました。 父の世代を特徴づける慎み深さも原因となっているのかもしれません」と書いている。
2012年に公開になった「Besa: The Promise」は、映画フェスティバルでの人気を維持しており、2014年のナッシュヴィル映画祭(Nashville Film Festival)では審査員大賞(Grand Jury Prize)を受賞し、2013年の4つの映画祭ではベストドキュメンタリー賞を獲得した。 しかし、商業的な成功はいまだ得られておらず、映画作成者や出演者らは、映画のメッセージが人々に十分に広まっていないのではないかと懸念している。
ノイマン氏は、「これらの人々が行った事柄について世界に知らせること、そしてイスラム教徒に対して存在する恐れは、人々の無知や熟考の欠如による結果であることを知らせること、これが私の人生における目標です」と語る。
「ライヒの敵」は、今まで25の都市で上演されてきた。主にアートハウスシアター、大学、音楽ホール、および博物館などが会場となっているが、9月9日(火)、PBSでも放映される。
この2つのドキュメンタリーの製作者らは、作品が教材として学校で上演されることも望んでいる。
「ライヒの敵」の共同プロデューサーであるクロンマー氏は、「私たちは、対話、そして映画によって人々が1つになることを信じています。 そして、この映画が、学生たちの未来の世代に対する教育に貢献するものとなり、イスラム教徒とユダヤ人の関係向上に役立つと信じています」と語っている。
www.enemyofthereich.com
www.besathepromise.com
 |
オマール・サツィルベイ(Omar Sacirbey)(osacirbey@hotmail.com)は、レリジョン・ニューズ・サービス誌の特派員で、ボストン・グローブ紙、ニューヨークタイムズ紙、ニューズウィーク・インターナショナル誌および他の雑誌に文化、ビジネス、政治に関する記事を書いている。 |