
 |
| 砂塵がアル・ズバラの遺跡を広く覆う。18世紀終わりの最盛期には数千人が住んでいたアル・ズバラは、22の望楼と防御壁に囲まれた城郭都市であった。 |
カタールの北西岸を見渡すと、湾の穏やかなコバルトブルーの水が、徐々に砂地になり、やがて小石の丘へと変化する。アル・ズバラの名前(砂の山)は、ここから来ているのだろうか。考古学者のアラン・ウォームズリー氏によると、アル・ズバラが歴史にその名を馳せた理由は別のところにあるようだ。
「アル・ズバラは確かに真珠交易の拠点として湾岸のどの街よりも守られてきましたが、それだけでなく、アラビア半島の都市計画を代表する優れた例でもあるのです」とウォームズリー氏。 しかも「この地域が沿岸貿易拠点としてどのように機能したのかをより詳しく知る手がかりとなる」素晴らしい事例なのだという。
アラビア半島といえば考古学者が千年単位で研究する場所。ここでわずか百年足らずで砂の上に富を築き、そしてまた砂に帰っていったこの場所が、ウォームズリー氏の言うような役割を果たしているとすれば驚きだ。 アル・ズバラは近くにある湾岸中南部の真珠漁場の恩恵にあずかり、1700年半ばから終わりにかけて豊かな交易の拠点として栄える。街の裕福な商人階級は、壮大な防壁を建て、数千人が暮らすこの街を囲んだ。 アル・ズバラは1800年代はじめに攻撃を受け、ほぼ破壊されているが、この街の歴史を紐解くと、産業化以前に「白い黄金」――すなわち真珠で栄えた湾岸経済の活力が感じられる。
 |
| アル・ズバラでは、時に「白い黄金」とも呼ばれた真珠で活気付いた当時の湾岸経済を解明するパズルピースのごとく、6万以上もの陶器の破片が見つかっている。 |
真珠採取の歴史は長い。 これまで発見された中で最古の真珠は、7500年も前のものと推定され、クウェートのアルサビヤとアラブ首長国連邦のウム・アル・クワイン2から出土している。 これらをはじめとする発掘物により、真珠は当時も宝飾としての価値が高かったことがわかっている。埋葬室の装飾などに使われたようだ。 「真珠は何世紀にもわたり、湾岸住民の考え方と生活様式を支配してきた」と記すのは2012年のロバート・A・カーター著『真珠の海(Sea of Pearls)』。
実際、アル・ズバラにとって真珠がどれほど重要だったのか、そしてアル・ズバラが当時どれほど重要な街であったのかは、カタール・イスラム考古学・遺産10カ年プロジェクト(QIAH)の研究命題だ。2009年に発足されたQIAHは、カタール博物館局(QMA)がコペンハーゲン大学と共同で主導したプロジェクトである。 1980年代と2000年代初頭の発掘作業は限定的であったものの、街の正確な広さと特徴はこれまでほぼ謎に包まれていた。その一方で、街の崩壊の鍵を握る出来事については十分な記録が残っている。 1811年、アル・ズバラは海からオマーン艦船の砲撃を受け、火災で消失し、滅んでいった。 住民は逃げ、街から人がいなくなった――というのが、歴史学の通説である。 一方QMAのプロジェクトでは、このいきさつに疑問を投げかける証拠が見つかっている。そして、より複雑で微妙な占領プロセスと、部分的な放棄、再占領の実態が示唆されている。
出典は少ないが、アル・ズバラの物語は1760年代、ウトゥブ族に属する部族の到来と共に始まる。ウトゥブ族は1600年代に中部アラビアから出現した部族の集まりで、その中には隣国バーレーンを支配したハリーファ家もいた。 ウトゥブ族はクウェートに移動し、本拠地を置いた。1765年には、約800隻もの真珠採取船を保有している。 影響力の拡大を決めたウトゥブ族はアル・ズバラに入植し、交易の拠点を築く。 湾岸の各地から商人がやってきた。バスラなど他の交易拠点は当時ペストの流行やペルシャの攻撃といった危機に見舞われたため、アル・ズバラに注目が集まった。
 |
| 1938年には壮大な要塞が建てられたが、それはアル・ズバラの栄光に陰りが見えてから100年も後のことだった。 現在は復旧中。 |
ウトゥブ族の指揮と、真珠採取船を武器に、アル・ズバラはあっという間に繁栄を遂げ、ものの10年で大掛かりな街ができあがった。 交易ルートは湾岸からインド洋、さらに東へと拡大した。 だが栄華は短命だった。 湾岸にはライバルの真珠採取場が出現。その中にはドバイやアブダビで昔から真珠採取に携わっていた者たちもいた。 湾岸の街の経済競争は激化。争いが絶えなかった現地の部族連合体の脆さも火に油を注いだ。
1770年終わりには、政治不安も増大していた。 海を隔てたアル・ズバラの北約40キロの場所では、ブーシェフルから来たペルシャ人がバーレーン島に支配の拠点を置いていた。 ペルシャ人にとって、アル・ズバラはにわかに出現した脅威だったので、1783年には敵対心が高じ、戦闘に発展した。 だがウトゥブ族が勝利を収め、バーレーンを占領する。 バーレーンに移り住んだアル・ズバラの住民の中で目立ったのが、ハリーファ家のメンバーだった。
 |
| アレクシス・パントス / QIAH / QMA |
| アル・ズバラが湾岸交易と農耕の大規模なシステムに組み込まれていたことを示す証拠。アル・ズバラ北フレイハにあるモスク跡。 |
人がバーレーンに移動し、それに伴って経済的な焦点もバーレーンに移動すると、今度は別の脅威が内陸から訪れる。 イスラム神学者、ムハンマド・イブン=アブドゥルワッハーブの下で団結した他の部族がアラビア中部から移動し、アル・ズバラを含む湾岸の街を脅かした。 島であったバーレーンは安全な場所だった。
一方世界の大国もこの地域に注目していた。 イギリスは、アル・ズバラ北東の湾岸の街、ラス・アル・ハイマのカワシム族を封じ込めようと躍起になっていた。カワシムは、アラビア湾からインド洋を航行するイギリス船に海賊行為を働いた首謀者としてイギリスの怒りを買っていた。 カワシムを攻撃するために、イギリスは、同じように自国の船を心配していたオマーンと条約を締結する。
 |
| アレクシス・パントス / QIAH / QMA |
| 崩壊のためにもう見ることはできないが、アル・ズバラは「文化が見事に融合した地であった」とカタール博物館局の考古学ディレクター、ファイサル・アルナイミ氏。 |
1809年、ワッハーブ派に影響を受けた部族はカワシムに加わりアル・ズバラを占領。 イギリス・オマーン同盟にとっては、一石二鳥のチャンスだった。 イギリスはすでに、カワシムに占領されていた他の港湾を攻撃していた。オマーンもアル・ズバラの攻撃を決意する。 1811年のある日、両国はアル・ズバラに乗り込み、砲撃を開始。 人々は混乱し、炎が街を焼き尽くした。
あまりにも突然の盛衰であったため、最盛期のアル・ズバラについては何の記述も残されていない。 攻撃から10年以上が過ぎた1824年、東インド会社のキャプテン・ジョージ・バーンズ・ブルックスはアル・ズバラを「大きな街だが、今は廃墟である。 湾岸に位置し、破壊前はかなりの貿易が行われていた」と記している。 これだけ示唆に富んだ、とらえどころのない歴史が、QIAHプロジェクトの背景にある。プロジェクトは、18世紀終わりに最も栄えた街の特徴について、全貌を明らかにしようとしている。 これまで4年間、外国人70人以上からなる国際チームが、毎年秋と冬にアル・ズバラに集まり、数ヶ月かけて、今や湾岸で最も重要な歴史的拠点の一つとされるアル・ズバラの研究、調査、発掘、記録に携わってきた。 チームはアル・ズバラの街の配置とその動向、どこでどのように人々が暮らし、短期間で財を成したか、答えを探している。
私は、こうした疑問を頭に置きながら、街に残されたものを見て回った。 面積は61ヘクタールで、サッカー場の12倍の広さである。 内陸側は、高さ5メートル全長2.5キロの防御壁の跡で隔てられ、防御壁には22本の望楼が等間隔で並んでいる。 地球物理調査とレーダー探査、昔ながらの発掘作業の結果、壁の内側には規則正しい碁盤の目状の道路と、住宅地(一軒は明らかに宮殿のように広い)、作業場をはじめとする各種用地の基盤が存在することが明らかになった。
 |
| アル・ズバラの市場や作業場跡地を案内するプロジェクト・ディレクターのインゴルフ・トゥーゼン氏(コペンハーゲン大学)。 過去4年間、外国人70人以上からなる国際チームが、毎年秋と冬にアル・ズバラで研究、調査、発掘、記録を行ってきた。 |
発掘作業を指揮するトム・コリー氏の指摘によると、ほぼすべての家に中庭が設けられている。 よく見ると、他の家にくらべサイズやデザインの点で明らかに大掛かりな造りの家がいくつかある。 「建築資材はさまざまでしたが、より精巧で重要度の高い建造物には質の高い石が用いられたことがわかっています」とコリー氏。 荒削りしたビーチロックを石灰ベースの石膏で塗り固めるという、基本的な建築技術を紹介してくれた。 あるコートハウスの石膏壁に、シンプルなダウ船のエッチングが施され、まだきれいな状態で残されているものがあった。街の歴史において海上交易が重要な役割を果たしたことを示している。
調査では、はかない歴史にもかかわらず、劇的に移り変わった幸運を象徴する何重、何段階もの建築方法がアル・ズバラに存在したことが明らかになりつつある。それはまるで急速な変化と一攫千金の希望にわいた19世紀アメリカのゴールドラッシュの街のようだ。 街が最大に拡張されたのは1760年代から1780年代の間で、一気に拡がった。だがその都市計画が、そこに暮らしていた漁民やその家族のテントや小屋などの小さな居住地を一切塗り替えてしまったことも明らかになっている。 中でも興味深いのが、浜辺の真上にある街の西端で発掘されたエリアだ。 ここには無数の柱や杭穴、かまど、炉が見つかっており、街の主だった建設期間に、テントや椰子の木で作った小屋など仮の住居が存在していたことがわかる。 つまり、毎年の「白い黄金」収穫期、すなわち5月から9月にかけての採取シーズンに、地元の真珠漁師以外に真珠を求めて出稼ぎにやって来た人々がいたことを示唆している。
一方、この街には真珠以外にも富の源があったことを示す証拠も出てきた。 海に近い街の中心部では、倉庫や市場が発見されている。 「鍛冶屋や職人作業などさまざまな物の生産や取引が行われていたことがわかります」と語るのは、発掘調査を指揮するマイク・ハウス氏。 屋外で土地を囲ったエリアに連れて行ってくれた。家畜に使ったスペースだという。 「アル・ズバラの人々は、真珠の街の労働者であるどころか、常に真珠以外でお金を稼ぐ方法を模索していた」そうだ。
発掘物を見ても、アル・ズバラの繁栄は真珠だけで築かれたものではないことがわかる。このことからチームは街の歴史の鍵とされたある出来事をも覆す理論を展開する。1811年の悪名高きオマーン艦隊の砲撃だ。 砲撃は、アル・ズバラのアルマゲドンはおろか、街に激変をもたらしたわけではないことが、調査で明らかになりつつある。 そもそも当時の街はすでに斜陽を迎えていた。 「構造物のさまざまな層を分析すると、アル・ズバラはオマーンの砲撃時にはすでに衰退しつつあったと思われます」と語るのはQIAHプロジェクトの考古学ディレクター、ウォームズリー氏。 「主要建造物のいくつかがオマーン軍の攻撃前に破壊され、見捨てられたのは明らかです」 こうした新たな証拠は、オマーン艦隊の攻撃前に、すでに多くの住民が街を去リ始めたことを示唆する歴史データを裏付ける形となっている。
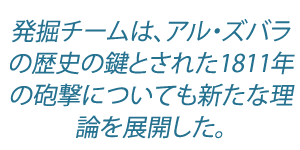 1811年の砲撃では確かに多くの住民が街を去った。少なくとも直後はそうだった。 だがまもなく街に戻った人もいる。彼らは仮の建物に住んでいた可能性があることから、1820年代に再入植があったことがわかる。この時期には、街を当初の約5分の1のサイズに縮小するような形で、崩壊した初期の建造物の上に、新たな内壁も建てられている。 同様に、商業地区も縮小して建て直されていた。破壊された建物のいくつかは解体され、廃物や劣悪な資材で再建されたものもあった。
1811年の砲撃では確かに多くの住民が街を去った。少なくとも直後はそうだった。 だがまもなく街に戻った人もいる。彼らは仮の建物に住んでいた可能性があることから、1820年代に再入植があったことがわかる。この時期には、街を当初の約5分の1のサイズに縮小するような形で、崩壊した初期の建造物の上に、新たな内壁も建てられている。 同様に、商業地区も縮小して建て直されていた。破壊された建物のいくつかは解体され、廃物や劣悪な資材で再建されたものもあった。
この地域では部族抗争も後を絶たず、1878年にアル・ズバラは再び攻撃に見舞われる。今回は、現代のカタールを建国し、一族が支配を続けた、シェイク・ジャーシム・ビン・ムハンマド・アル・サーニーによるものだった。 アル・ズバラは縮小された状態で19世紀末まで占領を受けるが、その後またしても見捨てられ、その後は散発的に人が住む程度だった。
 |
| 壷の破片を組み合わせて修復する保存修復専門家のナディア・ソーソリー氏。 右: 顕微鏡で腐食した硬貨の汚れを取り除き、隠れた図柄を調査するマリアンヌ・シュワルツ氏。 |
壁や屋根の破片に加え、これまでアル・ズバラで出土した中で最も多いのが陶器類である。 2009年以降、「シャード」と呼ばれる6万もの破片が調査されてきた。 その多くが遺跡の各地で見つかった貝塚から回収されたもので、街の外壁の内陸側にあることが多かった。 「シャードの山を種類と年代別に分けながら、解明していかなければなりません」と説明するのは、陶器研究家のアグニエシュカ・ビストロン氏。 「花柄の形が微妙に異なるなど、細部の違いで破片の年代がわかるのには驚かされます」 ビストロン氏は、ラス・アル・ハイマから出土したジュルファーの陶器、イラン、クンジの壷、液体を運ぶ細長い「魚雷」型の瓶、装飾が施された煙管、バーレーンのアーリ村の職人が作った特注の水槽など、実に多様な出土品を見せてくれた。中にはインドかイランのものと思われる出所不明の謎の黒い器もあった。 さらに18世紀から19世紀の中国磁器の破片や、かなり新しい部類に入るヨーロッパの磁器もあった。 青と白の興味深いボウルがあった。針金が鋲で接合してあり、ドリルで開けた穴がある。貴重で高価な物は壊れても捨てずに、修理して再利用していたことがわかる。
 |
| 考古学者が訪れた学生に、出土した陶器の洗浄と分類を指導している。 毎年約千人の学生が、遺跡と歴史を学び、発掘作業を見学しにアル・ズバラを訪れる。 |
調理や住人の食生活を明らかにする出土品もある。食事は当然ながら魚をメインとしたものだった。 だが意外なものもある。 膨大な数の魚骨の中に、今日のアラビア湾では非常に珍しいノコギリエイの骨があったり、一般的な魚でも今日よりかなり大きな標本が見つかったりしている。つまり、今日の漁業では、魚の十分な成長を待たずに捕獲していることがわかる。 真珠はカキの中にできる。カキの貝殻は食べた後に貝塚に捨てられた。発掘チームが見つけた貝塚は深いところで3メートルもあったという。 デーツを絞る道具も数々出土していることからデーツのシロップが作られていたことがわかる。米、小麦、大麦、そら豆、さらにはココナッツやモモ、アプリコット、クルミ、ぶどう、プラムといった果物の痕跡も、多様な交易ネットワークと購買力を示唆している。
 |
| アレクシス・パントス |
| 真珠ができかけているこの貝は、19世紀の建造物の外にカキの殻と共に捨てられていた。 真珠は、カキが侵入した異物の上に、炭酸カルシウムを主成分とした保護膜である真珠層を分泌形成することでできる。 |
真珠産業の解明に直結する出土品の中に、実際に真珠が含まれているケースはほんのわずかだ。 遺跡の出土品目録を追跡するホリー・パートン氏は、真珠の価値と運びやすさを考えると、これは当然予測されることだとしている。 住民は移動したり逃げたりするときに、真珠は真っ先に持っていたはずである。 一方、18世紀の真珠商人のチェストや、真珠を採るためのナイフ、鉄鉱石のヘマタイトでできた水滴型のダイビングウェイトなど、真珠採りや真珠商人が使ったさまざまな物品も見つかっている。 ダイビングウェイトは真珠採りが50メートル以上潜るときに使われた。 2014年12月にオープンする新たな国立博物館では、こうした出土品計200点以上が展示される予定で、すでにドーハに向けて出荷が済んでいる。
 |
| 左: ヘマタイト(鉄鉱石)製のダイビングウェイトは、真珠採りが50メートル以上潜るときに使われた。 上: ゴールドの鎖がついた真珠質の珠。 アル・ズバラを去った住人と共に持ち出されているはずなので、出土は非常に珍しい。 下: ガラスとスズでできたこの珠は、心棒に巻きつけながら重なりあった部分を伸ばしてなじませてある。 右: 平らな銀のリングは防壁の内側の貝塚で見つかったもの。 |
 |
左: 中国の器の一部と思われる磁器の破片は、後にペンダントのインレーに使われた。 右のガラス製のボトル栓と同様に19世紀のものと推定できる。 上: 上部を取り除いたコヤスガイの貝殻。宝飾かゲームの駒に使われた可能性がある。 これらはアル・ズバラの市場と商業跡地で見つかった。 |
出土品と同じくらい興味深いのが、アル・ズバラの街の構図で示唆される湾岸集落の特徴である。 シリア、ヨルダン、パレスチナで40年にわたり考古学を研究してきたウォームズリー氏は、アル・ズバラには、古く伝統ある中東都市に典型的な複雑で有機的な都市構造がないと説明する。 「イスラム都市は混沌と入り組んだ、無計画な発展を遂げているというのが従来の見方ですが、アル・ズバラにはそれがありません。 ここでは物事が整然としています。街のデザインと建設を司った中央権力が存在したのではないでしょうか」.とウォームズリー氏は語る。 誰がそのような指示を出したのかはまだ明らかではないが、そうしたビジョンや組織力は、一般住民の助言が得られるような教養ある個人のなせるわざだろう。
このような発見があったり、新たな疑問が湧くことで、湾岸の小さな街の都市考古学について、まだまだ解明が進んでいないことが浮き彫りになる。 当時を知る手がかりは現代の開発に埋もれてほぼ見えぬままだが、アル・ズバラは、この集落の人々がどのように生活し、働き、周りの人々と関わっていたかを教えてくれる特別な場である。
 |
| アグニエシュカ・ビストロン / QIAH / QMA |
| 街のレイアウトがほぼ判明した今、人々がどのように生活し、働き、他者と関わっていったかをアル・ズバラの例から学ぶことができる。 |
理解を深めるために、私は湾岸を数キロ北に行ったところにあるフレイハを訪れた。フレイハもまた、アル・ズバラのように「失われた」街であり、湾岸交易拠点のはかない幸運を歴史家が理解する手がかりを与えてくれる。 出土した陶芸品により、フレイハはアル・ズバラより歴史が長いことがわかるが、発掘調査ではフレイハも同じような発展とにわか景気、そして崩壊をたどったことが示唆されている。 フレイハが興味深いのは、主要な港から内陸に入ったところにある高地の泉を中心に集落が作られた点である。
だいぶ前に枯れたナツメヤシの切り株があることから、ここが農地であったこと、また、他では得られない季節の新鮮な農作物を港で提供することができたことがわかる。 こうした準備が各地で整い、湾岸を支える後背地の一部を成していた、と推測してもよいだろう。 19世紀の資料で「アル・ズバラとその周辺にある」20の要塞に言及があるが、このことは耕地制度制と囲い込みがかつて存在したことを明らかにした調査によっても裏付けられている。 こうした、淡水源に近い内陸寄りの小規模農村集落のネットワークは、湾岸の街の衛星都市としての役割を果たし、とくにアル・ズバラに重要な物資を提供してきた。
このように、アラビア湾南岸の小さな「都市国家」の交易ネットワークが、都市国家同士、そして都市国家と後背地をどう社会的、経済的に結びつけたかについて理解が深まった点こそ、QIAHプロジェクトの貴重な成果と言える。 さらに、1811年の砲撃は重要ではあったが決定的ではなかったこと、アル・ズバラは真珠交易以上の理由で栄えたことが判明したことも、同様に重要な成果と言える。
 |
| アル・ズバラの要塞は、修復後カタール博物館局のビジターセンターとなる予定。 |
そしてこのことは、街の衰退は単に地域的な出来事ではなく、複数の出来事の結果であることにも通じていく。 湾岸の真珠交易は、1920年代以降日本の養殖真珠の流入をきっかけに廃れていく。 1869年、スエズ運河が開通し、半球規模の交易ルートが確立すると、湾岸からの輸送は事実上世界相手ではなく地域的なものに縮小した。 そしてこの地域では、水源の過剰利用により、干ばつと農業の衰退が加速した。 アル・ズバラでの保存活動は今のところ、外壁、望楼の一部、最大の屋敷構内にある住居数カ所を修復し、破片を組み合わせるに留まっている。 まだ再建を果たしたものはないが、壁は古い石膏の破片をできる限り貼り付け、必要に応じて新しい石膏を塗り、安定した状態を保っている。 250年前の最盛期にアル・ズバラが誇った姿を今日に再現するきっかけを与えてくれたこのプロジェクト。アル・ズバラの砂道を歩き、かつて住人を守った防壁の傍らに立つ日が1世紀ぶりに実現する。
「アル・ズバラは文化が見事に融合した地です」とカタール博物館局の考古学ディレクター、ファイサル・アルナイミ氏は語る。 「カタールだけでなく、この地域全体の歴史に新しい光を注ぎ込んでくれる貴重な発見です。 この豊かな遺産を世界に公開できることを光栄に思います」
 |
ジェームズ・パリー (www.jamesvparry.com) は、アラビア半島の歴史と遺産を専門とする歴史家、作家、講師。 中東の国々で働き住んだ経験がある。現在はイギリスのノーフォーク在住。 |
 |
ダン・ブリトン (brittondan@hotmail.com) はフリーランスの写真家であり、コペンハーゲン大学の考古学者。カタール博物館局を代表して、スタジオ撮影、現地撮影、カイトフォトを駆使しながらアル・ズバラでのカタール・イスラム考古学・遺産プロジェクトの写真撮影を担当している。 |