青銅器時代のバビロニア神話エヌマ・エリシュによると、すべての陸地が海であった原始の沼地にマルドゥク神が土と葦で地面を作って、世界が始まった。 こうした場所はほんの50年前まで存在していた。
イラクの南部にはかつて2万平方キロもの湿地が広がっていた。私は、かつて世界の中でも手付かずの損なわれない自然を誇ったこの地に、1967年の10月から11月の1ヶ月間滞在することができた。 時に信じがたいようにも思えるが、今日のイラクは、かつてユーラシア世界の中心地であった。 メソポタミアとシュメールは、何千年も前にここで培われた文明の発祥地だった。
「メソポタミア」は「川と川に挟まれた土地」を意味する。川とはチグリス川とユーフラテス川のことである。 合流点には湖や水路、川、島、森のある湿地帯が広がり、人間の3~4倍も背の高い葦が群生する。 ここがエデンの園であったという人もいる。
湿地帯の外には、その縁を取り囲むようにウルク、ウル、ラルサといったシュメール都市の遺跡が今も見て取れる。 文明は絶え、消滅した。だが例外があった。 湿原には自称マアダンという人々が住んでいた。マダンは大まかに「平地の住人」を意味し、英語ではマーシュアラブ(Marsh Arab、湿原のアラブ人)として知られる。
マアダンはアラビア語の方言を話すが、彼らの多くはおそらくシュメール人の直属の末裔であるだろう。 私の訪問した時の人口は、25~50万人であったと推定される。
湿原の訪問を許された最後の欧米作家はウィルフレッド・セシジャー(名著『湿原のアラブ人』と『Arabian Sands』の著者)で、それも1950年代である。だから湿原に行くための正式な許可証を取るのは難しいと思われた。 実際取得には3週間もかかった。バグダッド市長の協力もあり、最終的に必要書類を発行してもらうことができた。 イラク政府はすでに湿原を干拓すると脅し、古代の生活様式を滅亡させようとした。 このような状況は逆に、私の意欲を強めるのだった。
当初の計画では、小さな商人の村マジャール・アル・カビールからガイドと共に湿原用のカヌーに乗って出発するはずだった。 なるべくシンプルに行こうと、舟に載せるのは自分とガイド、カメラ、ショットガン2丁、そして現地の食事に飽きた時のために、どういうわけか地元の食料品店で見つけたノルウェー産イワシの缶詰200個だけにしようと思った。
だが当局は、護衛のために武装した兵士を連れて行けという。 マアダンたちは政府当局のような出でたちを嫌うことを私は知っている。兵士がいれば私の作業は困難になるのも目に見える。
カヌーは平底のモーターボートに変えなければならなかった。それと共にボート漕ぎでガイド、通訳をこなすイブラヒムが同行することになった。彼は湿原育ちで、英語はアメリカ人が所有する砂糖工場で学んだという。 同行する兵士はかなり年配であることがわかった。皺が刻まれたやさしい顔立ちで、骨董級のライフルを持っている。 まだらになった茶色の制服を着た彼に、怖そうな印象はなかった。
イブラヒムはこの時、漕ぎ手の補助がほしいと言ったが、それなら自分にもカメラマンの補助が必要だし、 年寄りの兵士にも補助が必要になるだろう、とごまかした。 幸い彼は大きな笑いで応え、その雰囲気のまま、私たちはマジャール・アル・カビールを出発し、湿原に向かって泥水を南下し始めたのだった。
とても美しく涼しい、早春の朝だった。イラク官僚とのやり取りで生じたストレスからやっと解放された私は、うれしさと、始まったばかりの冒険への期待に胸を膨らませていた。
だがこの幸福感も長くは続かない。 その直後、後方の川辺に土埃が立つのが見えた。ジープがけたたましく追いかけてくる。運転手はクラクションを鳴らしている。 ジープの男は立ち上がり、必死で手を振っている。 私たちは舟を岸に寄せ、男を待った。
ジープは停車し、若い浅黒い肌の男が出てきた。 男は安っぽい黒のスーツに白いシャツ、黒いネクタイを身にまとい、磨かれた黒い靴を履いていた。 ためらいも説明も、謝罪もないまま、男は「サラーム・アレイクム」と言い、私たちの舟に乗り込んで座り、タバコに火をつけた。
私は言葉を失ったまま、男を見つめていた。 男は泣く子も黙るイラク秘密警察の非公式な制服を着ていた。そしてジャケットの下にはピストルの膨らみが見える。 当然だと言わんばかりに、彼は私たちに同乗したのだ。 無駄だとわかっていたが、気持ちを鎮めるために怒りを爆発させるふりをした。 イブラヒムは肩をすくめ、私にささやいた。 「村に着いたら、船は島に停めよう。タバコと食料を与えて、我々は別のカヌーで作業をしよう。」
イブラヒムの案はうまくいった。補足すると、最初は張り詰めた空気が流れていたが、警察官は好意を寄せ、私たちは仲良くすらなった。だから私も自分で心置きなく仕事をすることができた。
私たちの小連隊が落ち着き、いくぶん仲良くなった頃、舟は泥水を抜け、狭く深い透明な水路に差し掛かっていた。両岸には7、8メートルもある背の高い葦が茂っていた。 全員が沈黙した。 私たちは湿地帯に突入した。
最初は、エンジン音と見たこともない鳥の金切り声しか聞こえてこなかった。 ふと、向こうの方で、何艘もの小舟が葦原を出入りするのが目に入る。 彼らこそ、私たちが初めて目にしたマアダンだった。 彼らは葦や食べられる草を集めに忙しく動き回っていた。中にはヤスで漁をする者もいた。
だが私たちの舟に制服姿の男を見つけるやいなや、何人かは舟を旋回し、逃げていった。2年間の徴兵に連行されると思ったのだろうか。
まもなく、風のうわさか、私たちの正体は到着前からマアダンに知れ渡っていた。 警察の手入れではなく、外国人の撮影取材だと知ると、逃げることはしなくなった。
水路は広がり、沼に差しかかる。 右側に、アル・サヘイン村の葦小屋が見えた。 私たちは周辺で待ち、村の長が出迎えの準備を整えるのを待った。 この辺の習慣だとイブラヒムは言う。
まもなく知ったのだが、出迎える側の準備とは、火をおこし、タバコを数箱用意し、ご飯を炊き、女性にパンを焼かせ、鶏を1、2羽ほど殺すか、新鮮な魚を捕り、ムディフ(ゲストハウス)の掃除をし、きれいな葦マットを床に敷くということであった。
待っている間、村をじっくり観察することができた。 小屋はそれぞれ小島の上に立ち、重なった葦を束ねて作られていた。 造りは古代のもので、建物の形はシュメール時代に由来する。
大小のカヌーが村を縦横に動き回り、男性、女性、さらには子供までも竿や櫂で漕ぎ回る。 小屋のそばでは、大きな水牛が泳ぎ、浮かび、島によろよろと登ろうとしている。水牛は湿原の人々の暮らしに欠かせない存在だ。
紀元前4000年にシュメール人がこの地域で家畜化した黒く大きな水牛は、ミルクやヨーグルト、肉、革を提供した。さらに糞は燃料に使われた。 糞は塊にして葦小屋の壁一面に貼り付け、乾燥させてから使う。 臭うと思うだろうが、 悪臭は全く気にならなかった。
ついに、1艘のマシュフ(カヌー)がこちらに近づいてきた。年配の男が降り、手を振って言った。 「どうぞどうぞ。ムディフへようこそ」 私たちは遠慮して見せた。申し出を取り下げるチャンスを与えようとした。もちろん本気で断っていたわけではない。
老人が熱心に招くので、私たちは喜んで応じたのだった。 彼の先導で、私たちは一番大きな島の一つに向かう。そこには大きく見事なムディフが立っていた。 長老、シャイフ(イラク政府がこの役職を正式に禁じている)の手助けで私たちは岸に降り立つ。長老は広い葦の家屋に案内してくれた。
靴を蹴って脱ぎ、中に入ると、 そこには薪が燃え、慣習どおりアラブ式のコーヒーポットが準備されていた。 私たちは腰を下ろし、お互いのことを尋ねる。「ごきげんはいかがですか。家族はいかがお過ごしですか。作物の調子は?動物の調子は?」と延々に続くのが慣習である。
湿原でも他のアラブ世界と同じように、来客には甘さがなく苦く濃い、カルダモン風味のコーヒーを出す習慣があった。 通常、一人の男性が小さなカップにコーヒーを注ぎ、注ぎ足す。 毎回数滴しか注がないが、3杯目を飲み終えたところで初めてカップを振り、もう十分であることを告げる。 その頃にはカフェインが少し効いているかもしれない。
主人は客の前にタバコを1箱置いた。とても寛大な振る舞いだ。 コーヒーの後には、とても甘い紅茶がグラスで出される。さらに紅茶を飲み、タバコを吸い続け、会話が始まり、止まり、また始まる。
長い沈黙があってもマアダンは気にしない。 魅力的な特徴だと思った。 この間男たちがひっきりなしに行き来していた。そして、女性も入り口から覗いている。
お盆に山盛りになったご飯が出された。次に焼き魚とスープがお盆に乗って出された。 スープは皆で回し飲みしにする。一人一人、たっぷり飲み込んだ。 スープはご飯の上にもかけた。そして発酵した水牛のミルクが回ってきた。
私たちと村の要人は葦のマットの上にあぐらで輪になって座り、先に食事を頂いた。 食べ物はすべて右手で食べる。 ご飯を手の平でこねて丸め、親指ではじいて上手に口の中へ放り込む。 ぎこちなく指で口にご飯の塊を押し込もうとする私を、男たちがこっそりと見ていることに気づいた。 毎回恥ずかしいくらいのご飯がマットの上に落ちてしまう。 これが少し笑いを誘ったが、ほとんどが食べることに集中していた。
親切な主人はこの際食事はせず、座りもしない。その代わりいつでも手助けできる様子で、そばをうろうき、私たちを見守っている。 苦戦している私を見て、主人は親切にスプーンを持ってこさせたが、私はスプーンは使わなかった。これが皆を喜ばせた。 イブラヒムは私を喜ばせようとこんなことを言った。「あっという間に仲間になれますよ」
食事を終え、手を洗いに外へ出た。 一人ずつ石鹸が渡された。水差しから手に水を注いでもらい、すすいだ。 ムディフに戻ると、私たちが座っていた食物の周りの席に、女性や子供、マアダンの階級では下層の人々が一気に集まり、 山のようにあった食べ物を一瞬にして食べ尽くした。
出された食事はすべて、ご飯の上にのせて出された。 何らかの野菜を他の食材と合わせて調理したものだった。 スパイスも使われていた。料理はいつも美味しそうに見えた。 私が常に空腹だったことも関係していただろう。
空腹なのは、年長者が食べ終わって立ち上がると、ほか全員も立ち上がるためだ。皆私の半分ほどの時間で食べ終えるので、 皆が席を立つ頃、私の腹は半分しか満たされていないのだった。
にもかかわらず、マアダンと過ごした期間、私は普段よりも体の調子が良かった。 セシジャーらの報告に反し、マアダンたちも病気があるようには見えなかった。 活動的に肉体を使って過ごす生活に加え、魚、コメ、野菜、時々肉という健康な食生活も手伝った。 だがタバコはどうしたものか……
昼食後はいつものように甘い紅茶を飲み、タバコをふかし、会話をする。 こういう時はタバコを吸わない人も、コーヒーや紅茶のように、一緒にタバコを吸うのがマナーだった。
個人的なことはほとんど話さなかったが、主人は旅の理由を聞き出した。私たちの目的にやましいところがないと実感できたようだ。 湿原では舟よりも早く噂が広まった。
夕暮れの2時間ほど前になり、私たちは出発した。別に出発したかったのではなく、シャイフが破産しないようにするためだった。 すでに私たちのもてなしに大枚をはたいている。私たちがこれ以上滞在すると、慣習上彼はさらにお金を費やすことになる。 差し出されたタバコはには手を付けず、気持ちばかりのお礼にノルウェーのイワシ缶をいくつか置いていった。
村の全員が見送ってくれた。こうして私たちはこの小さなメソポタミアのベネチアを後にした。 心温まる経験だった。
私たちの一日はこんな風に過ぎていった。 葦原や葦の群生、水路、沼、湖をボートで抜ける。 居住地のそばでは、大人も子供も葦を集め、食べられる植物をとり、ヤスや網で魚を捕る。
陸地の端近くに住む人々は、魚や葦から作ったマットを交換したり売ったりしている。 これは必需品を外から手に入れるための唯一の手段だった。 舟を造るための木と穴をふさぐビチューメン、砂糖、塩、火薬、タバコ、布類などである。
人がいない場所には、アヒルやモモイロペリカン、サギ、そして知らない鳥がたくさんいた。 水牛の群れが水中をゆっくり歩いたり、水が深い所では和やかに泳いだりと、自由に動き回っている。
水上を動き、各地を訪問し観察していくうちに、「すべての陸地が海だった」世界に住むマアダンと、すべての陸地が砂だったところに住む砂漠の遊牧民、ベドウィンとの間には多くの共通点があることが明確になってきた。 私はサウジアラビアのベドウィン族とも過ごしたことがある。マアダンの生活の細部にベドウィンを思わるところがあった。
ある日、アル・チデーという村に着いた。 犬が吠え、私たちの到着が知れた。 ここではどこの家にも番犬がいる。これは厄介だった。特に夕暮れ後が。 家の者が犬をなだめない状態で他人の家に入ったり、太い棒を持たずに入ったりすると大変なことになる。
舟の漕ぎ手は村の長老の親戚で、今回は村の外で待たずに彼の家へ直行した。 気さくな湿原の老人は、私たちの到着をなぜか知っていたらしく、準備はすでに整っていた。 この地域の衣装であるビシュト(マント)とグトラ(頭に巻くスカーフ)をまとい、長老と家族全員が私たちを出迎えてくれた。
女性とは他のアラブ地域のどこよりも自由に仲良くなれたが、私が家族の女性と握手をしたのはこの時が最初で最後であった。 陽気なチーフの妻は、短い間だが私たちの食事につきあってムディフの中でも同席してくれた。今回のごちそうは、チキンがメインだった。 魚かチキンが出るのが普通で、時々ラムも振舞われる。
このムディフでは1泊以上の滞在を勧められたこともあり、チーフの家族は舟から私たちの荷物を下ろし、ムディフに持ち物一式と備品を積んでくれた。 盗難の恐れはほぼないにしろ、来客の荷物が盗まれてはいけないとの配慮だった。
湿原での生活で何が一番大変かが徐々にわかってきた。 睡眠不足とプライバシーの欠如である。 夜明けに起きて撮影をしたかったので、睡眠は必要だった。しかも湿原の昼間はとても長かった。
大変だった。 大事な客人がいるからと、村の人は早々に帰宅して寝る気にはならなかった。 それは私たちが去ってからできる。 だから宴と座談は午前2時、3時まで続き、私は寝袋に座ったまま寝入ってしまうのだった。
朝5時には太陽が上り、起床する。 主人は起きて朝食の準備をしていた。 私はカメラ一式を持って玄関から抜け出し、すっかりなついた番犬を足元につけて出かけた。 湿原が「時間を超越している」と誰かが言っていたのが、初めて理解できた。 水面を覆う朝もやの中に、暗くピンクに光るものがある。
何一つ動かない。 遠くで蛙が何匹か鳴いているが、他に音はない。 葦の小屋と島は水にはっきりと映っている。 その向こうには、背の高い葦がぼんやり見え、その上にはペリカンの群れがどこからともなく飛んできて、去っていく。
そして柔らかに水を切る音がする。 釣り船が葦の間から現れた。鋭く、美しく上に曲がった船首が水をサッと切って走った。 漁師は静かに挨拶をし、私も挨拶を返した。 だが魔法は解けていなかった。 水牛が水面を揺らし、何頭かが静かに潜った。 葦の家屋からは煙が立ち上がる。小さくささやく声が聞こえた。 私は取り憑かれたようにシャッターを切った。
毎日私の生活は何らかのパターンを繰り返していた。 朝食前と時には朝食後、イブラヒムと私はカヌーを借りて、二人で出かけた。私は写真を取り、人と話し、湿原の暮らしを観察した。軍人と秘密警察は放おっておき、自由に寝、食べ、茶やコーヒーを飲ませ、一日中タバコを吸わせてやった。 実際彼らの存在は無に等しかった。
日が高くなりすぎると、日差しが強すぎて良い写真が撮れなくなるので、荷物を舟に積み込み、次の場所に移動し、アヒルを撃って食べた。 アヒルはたくさんおり、食事の足しにもなったし、寝泊まりさせてくれる人への土産にもちょうどよかった。
湿原では、鋭いユーモアにあふれる人々にめぐりあった。夕方の座談では、私がマアダンのやり方で何かをしたり、貧弱なアラビア語を振り絞って話したりする度に大きな笑いを誘った。 中には失礼な言葉を教えてくれる人もいた。 そうした言葉を使えば緊張感が一気に解け、 人々は爆笑するのだった。
また、家族間の不和に危うく巻き込まれそうになったこともある。血なまぐさい抗争に発展しかねず、村と村が敵対しそうな状況だった。 実際はそうだったのかもしれない。 私には知る由もない。
中央の湿原にある小さな村に着くと、何か普通ではない気配を感じた。 コーヒーや紅茶を出す気配りがやっとだったようだ。 一方でカヌーが行き来し、よそ者の私にさえ、何か心躍るような感覚が伝わってきた。
落ち着かないまま軽食を食べていると、イブラヒムは村の娘が昨晩近くの部落の少年と結婚したという。お見合い結婚だ。 後でわかったのが、その娘には同じ村に幼馴染のボーイフレンドがいて、娘は彼を心から愛し、結婚を願っていた。だが彼女の両親はお見合い結婚を強要したのだった。
イブラヒムが知った話だと、娘は結婚式を終えたが、その夜に新郎を置いて飛び出し、ボーイフレンドの元に身を寄せたという。
娘の家族はすっかり面目を失った。 娘が戻らなければ、償いとして大量の水牛とお金その他を捧げなければならない。 2つの村の委員が集まり議論したが、そうこうしているうちに銃を巻き込む事態となった。 問題はどの世界でも生じる。ここ、「天国」でも。
私たちは旅を続けたほうがいいとの提案を受け、 その通りにした。 この事件が解決したかどうかは、その後もわからなかった。
湿原の人々にとって最大の厄介者は、何千もの群れになって湿原をさまよう巨大なイノシシだろう。 ひどく不機嫌な獣で、危害を加えなくても、驚いただけで攻撃してくるし、驚かないのに攻撃してくることもある。 湿原で生じる殺傷の3分の1が、イノシシによるものだった。湿原のアラブ人(ムスリム)はイノシシを食べることすらできない。

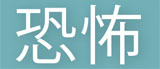
1990年以降にマアダンの地に起きた出来事は痛ましいものだった。 イラク軍をクウェートから追い出した米英主導の戦争を支援した報復として、イラクの独裁者サダム・フセインは、マアダンの湿地にダムを造り、湿原を焼き、湿原だけでなくイラク南部全土の村々を爆撃した。 湿原とマアダン、マアダンの文化、貴重な自然破壊を全面的に破壊することがサダムの目的であった。 家に留まったのはほんの一握りしかいなかった。
だが、サダム・フセイン政権が2003年に崩壊すると、マアダンたちは政府の行動を待たずに、自分たちで堤防を破壊し、湿原に水を戻そうとした。 その後、組織的な回復作業が行われ、現在では湿原の30~40%に水が戻っている。だが、イラク北部、シリア、トルコのダム建設プロジェクトは、水量調節が新たに厳しく規制されている。
にもかかわらず、マアダンの生活様式は消失した。 現在マアダンの人口は4万人以下で、その多くが湿原のすぐ南にあるバスラという町に住んでいる。 研究者がマアダンに村に戻りたいかどうかを尋ねると、決まってこんな答えが帰ってくる。「はい。でもテレビや電話、病院、学校、電気もほしいのです」
得られたいくらかの資金で、夢見る建築家やデザイナーが、個人部屋やキッチン、バスルーム、下水道、ソーラーパネル、衛星アンテナ、そしてもちろんインターネットが装備された葦の家を考案したが、 それが実現したとしても、5000年の生活様式は戻らない。 この先誰も湿原には住まないということではない。だが、マアダンが現代的な葦の家で衛星放送を観、アルミ製のカヌーで観光客にほぼ消滅した故郷を見せて回る可能性はあるかもしれない。 |
湿原のアラブ人に喜ばせるには、イノシシを殺すこと以外になかったので、私たちは毎日イノシシを探しまわった。 それに、殺せないにしても、一度見てみたかった。 イノシシの跡を見つけ、夜には鳴き声が聞こえたが、残念ながら遭遇することはなかった。湿原での最後の夜までは。
私たちは、前日に豚がいた深い茂みや葦を、一日中小さなカヌーで探しまわった。 何も見つからないので、夕暮れ時に舟で引き返そうとしたその時だった。
私の左側、浅く水に浸ったエリアの端に水牛が動いているのが見えたので、イブラヒムに伝えた。 イブラヒムは凍りついたように驚いて言った。「あれは水牛ではない。 イノシシだ」。 6頭いた。3頭は巨大で暗闇では水牛のように見えた。
イブラヒムは銃を構えた。その日同行した地元の湿原住民も銃を構えた。 私はカメラ2台と300mmのレンズを手にとった。
「攻撃してくるぞ」。イブラヒムが囁き、撃鉄を引いた。 私は望遠レンズをイブラヒムの肩に当て、曲がった醜い牙から目を離さずにぼやけたシーンを撮り続けた。 辺りはすっかり暗くなり、身を守らずに撃つのは正気でないことに気づいた。 暗すぎて撮影も無理だった。
私たちは身動きせずに待つしかなかった。 1頭が鼻を鳴らした。するとイノシシは向きを変え葦へ消えていった。
周りから安堵の深い溜息が漏れた。私はふらついていた。いや、震えていた。 恐ろしい瞬間が鮮やかに記憶に刻まれた。 また、湿原では、本当の天国を見つけたかのような瞬間もあったが、この事件は天国はどこにもないことを私に思い出させてくれる出来事であった。
もう存在しない古代のライフスタイルを経験できた私はとても幸運だったと思う。私は、マアダンの寛大な厚意とやさしさを決して忘れたことはない。
  |
ノルウェー生まれのトー・エイグランド(www.toreigeland.com)は、フリーランスのライター、写真家として人生のすべてを旅に捧げる。彼は本誌にも長年貢献し、多くの出版物にも寄稿してきた。 現在はフランスの自宅を拠点に、フォトジャーナリズムから本の執筆に方向転換。この度、著作『All the Lands Were Sea』が初めて出版される。だが、写真も諦めないと誓っている。 |