
「10年前のことです。忘れもしないできごとがありました」。 アハメド・ボーグは、サウジアラビア西部、タイフの高地からくすんだ砂漠の景色を眺めている。 「山の中にあるアブハーにキャンプに出かけました。 道路が舗装される前でした。 町からかなり高台にある荒野でした。 夜が明けるころ、父が血相を変えて私たちを起こしました。 「サルだ!」と叫ぶのです。 「急げ。荷物をまとめろ!」 できる限りのものを持ちました。 100頭ものサルがやってきたのです。 サルは果物も食料もすべて持ち去りました。 その後、靴やおもちゃなど、物を取りに谷まで下りたのですが、 衝撃でしたね。 これがきっかけで、サルたちに興味がわいたのです」。 子供の頃の興味が、彼の専門分野となった。
現在、サウジアラビア国立野生研究センター(NWRC)で所長を務めるアハメド・ボーグは、幼い頃に衝撃を受けた僻地の侵入者――マントヒヒの世界的権威である。
 |
| 岩だらけのサラワト山脈は、マントヒヒにとって理想的な生息環境だ。 約65%が野生のままであるが、35%はタイフ西のハイウェー15沿いなど市街地付近に生息し、餌を得ている。 |
アフリカで見られるようなサバンナヒヒ、チャクマヒヒ、ギニアヒヒとは違い、マントヒヒはエチオピア、エリトリア、ソマリアから海を超えてイエメンやサウジアラビアの降雨量の少ない山々まで、紅海の両岸に生息する。 ホモ・サピエンス以外では、アラビア半島固有の唯一の霊長類である。
マントヒヒは、飲み水として表流水を必要とし、岩がちな斜面で眠る。 35万頭が生息するとされるサウジアラビアでは、イエメンとの国境から紅海に沿って約800キロ北上したところにあるサラワト山脈でこうした条件がそろっている。 細長い地帯だ。 サラワトの東の砂漠には崖はあるが水がない。サラワトの西の沿岸低地は水があるが崖がない。
ボーグの故郷タイフは、サラワトの標高1900メートルのところに位置する。 マントヒヒに絶好の環境であるため、タイフはマントヒヒで有名な町になってしまった。 とくに西側周辺では、岩だらけの斜面を100頭単位で跳ねまわり、公園の周りをうろつき、その姿を楽しむホモ・サピエンスからおこぼれを巻き上げる始末だ。
ボーグは数キロ北のアル・ハダまで車で連れて行ってくれた。アル・ハダはメッカに通じるハイウェー15が、正確なヘアピンカーブを描いて崖を下り始めるポイントにある。 壮大な砂漠の景色が目の前に広がる。私たちは、老若男女のマントヒヒが肩を並べて岩の上で跳ね、さらに4車線のハイウェーで跳ねる様子を眺めた。まさに道路で踊っているかのようだった。 「動物にエサを与えないでください」と書かれた看板の真下では、運転手が車を止めてフルーツやパン、残り物を車の窓から放っていた。マントヒヒの一団が金切り声を上げて、宙返りしながらボンネットや屋根に群がった。
 |
| 上: 道路脇で跳ねまわるマントヒヒを見る家族。 下: オス1頭にメス4頭がついているが、マントヒヒは社会的に単雄群に分かれて生活する。 |
 |
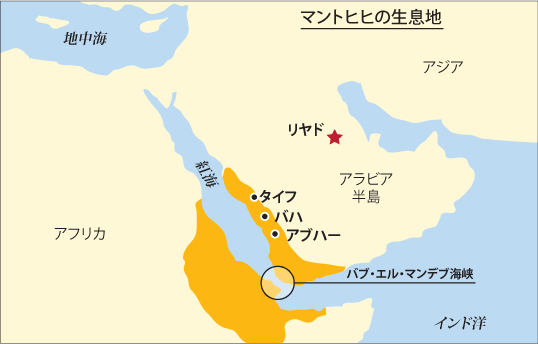 |
| 紅海を渡る |
アフリカのヒヒがどうやってアラビア半島に行き着いたのだろうか。 それともアラビアのヒヒがアフリカに行き着いたのだろうか。 霊長類学者を何十年にもわたって悩ませてきた命題だ。 ハンス・クマーは1995年の代表作『聖なるヒヒを求めて』(原題:In Quest of the Sacred Baboon)の中でこう記している。「不可解な状況だ。 マントヒヒの起源は(紅海の)どちらか一方であるはずなのだ。 なのに、それがわからない」
紅海の両岸に生息する他の動物は、互いに大きな違いがある。 例えばオオカモシカやヒョウは、どちらもアフリカとアラビア半島で顕著な身体的・行動的違いが見られる。 だがマントヒヒは本質的に同じだ。 本質的に同じであるということは、マントヒヒが長期に渡って孤立していたことを意味する。マントヒヒが現在の形に進化し、その後比較的最近になってから現在の生息地に広がったようなのである。
クマーはアフリカ起源説を支持し、ヒヒを崇拝したと知られる古代エジプト人が、海を超えてヒヒを連れてきたという興味深い考えを提案している。 (紀元前1500年頃、ハトシェプスト女王がアフリカの角にあったとされる「プント国」に遠征隊を送り、生きたマントヒヒを持ち帰ったとの記録がある。) クマーは、紅海の海上貿易が盛んであった頃のある時点で、ヒヒが船から跳び下り、アラビアの紅海上にそびえる山々に新しい集団繁殖地を作り上げたと提案する。
彼の説が正しければ、アフリカとアラビアのマントヒヒの個体群は、遺伝子上同一であるはずだ。 だが彼の説は観察から導かれたもので、DNAテストが普及する前のものだった。
リヤド郊外にあるキング・ハリード野生研究センターの実験室では、イギリスの遺伝学者ブルース・ウィニーの研究チームが2004年、アラビアのヒヒのミトコンドリアDNA(mtDNA)が多様であることは、アラビアでの集団繁殖が2万年以上前に生じたことを意味していると発表した。人類の文明誕生のかなり前である。
つまりヒヒは自力で移動したことになる。 でもどうやって移動したのか。 ゆっくりとエチオピアから北上してエジプトに移動し、シナイ砂漠を横断して北からアラビアに入ったのだろうか。 そうであれば、マントヒヒが現在生息する北端の個体群は、南の個体群と比べて遺伝子上アフリカの個体群に近いはずである。 だが、ウィニーの分析では、両岸の分布の北端にあるエリトリアとタイフで採取したサンプルが、遺伝子上大きく異なることが判明した。
そこで科学者は南に目を向けた。 紅海でジブチとイエメンを隔てるバブ・エル・マンデブ海峡は、幅が30キロしかない。 世界の海面がもっと低かった氷河期、この海峡は50万年にわたり幾度か大陸間をつなぐ陸橋の役目を果たしたと思われる。このことから、ウィニーと研究チームは、ヒヒが13万~44万年前にアフリカからアラビアに渡った可能性があると結論づけている。
さらにタイフでアハメド・ボーグと親しく研究を共にしていた京都大学の霊長類学者、庄武孝義氏も、大昔の進化の過程で、ヒヒの祖先がバブ・エル・マンデブ海峡を超えてアラビアに渡ったことを示唆している。 マントヒヒはその後、アラビアで数十万年もの間孤立していたが、その間に顕著な特徴を進化させた。そして東アフリカの山々に「戻った」というのである。 最近の分析でアフリカとアラビアのマントヒヒの遺伝子が異なることがわかったのも、これで裏付けられる。 庄武氏の研究はまだ準備段階であり、彼の仮説はまだ検証されていないが、期待のもてる興味深い可能性を秘めている。 アフリカから島流しになったのではなく、アラビア生まれなのかもしれない。 |
マントヒヒは、木の上に住むしなやかでスレンダーな動物とは違う。 背は低くずんぐりして、力がある。 成熟したオスの体重は30キロにもなり、長く四角い鼻口部を開けると、5センチにわたって犬歯がむき出しになる。 頬、肩、上半身をマントのように覆う毛羽立った銀色のたてがみと、隆起した眉弓の下で鋭くにらむ細い目――その外見のすべてが大きさと強さを物語っている。
メスは半分の大きさで、茶色の短い毛はあるが、オスのような印象的なマントはない。 社会的にはオスが支配し、メスを周りに並べてヒヒ社会の一雄多雌の構成要素、つまり「単雄群」(omu: one-male unit)を形成するとボーグは説明する。 ハイウェー路肩でヒヒの騒ぎを眺めていたとき、
ボーグは、いくつかの単雄群があることを指摘した。 それぞれで、1頭のオスが2~8頭のメスとその幼獣を従えていた。 さらに大きなグループもあると彼は説明する。 2つか3つの単雄群が一族として共に暮らし、餌を食べる。2つか3つの一族が一団として密接なつながりを維持する。数団が1つの群れをなす。1つの群れは100頭以上の個体で構成され、毎日集団で寝る場所から食べる場所、休む場所を移動する。
各グループの中では、同意と強制のもとで社会秩序が維持される。 メスがはぐれないように尻尾を持って引っぱろうというオスの姿も珍しくはない。 ボーグによると、この行為はメスをめぐって戦うアフリカのヒヒのオスにはない習性だ。 「アラビアの乾燥した環境への適応だ。 メスを群れに従えておくほうが、メスを取り返すために別のオスと戦うよりもエネルギーを使わなくて済む。 エネルギーの温存が第一なのだ。」
専門知識が豊富なボーグだが、30年に渡る研究のほとんどは単独で行なってきた。 アフリカ種と比べて、アラビアのマントヒヒの個体群について出版された学術論文は、
 |
| マシュー・テラー |
| 「ヒヒの餌付けを止めさせなければならない」とアハメド・ボーグ(上)。 ヒヒが人間の食べ物に部分的または全体的に依存して生きる片利共生は、社会的ストレスの原因となっている。 メス(下)は、片利共生的な過食で出生間隔が短くなり、個体数が過剰になっている。 |
 |
ほんの一握りである。 まるで、前世紀に人間が他の自然界への理解を深めている間に、マントヒヒが取り残されたかのようだ。 スイスの霊長類学者、ハンス・クマーは、これについて仮説を立てた。 マントヒヒ研究の草分けとして、彼はまず1960年代にエチオピアのマントヒヒを研究した。哺乳類の大半が、人間には認識できない香りや、性的だとは認識しがたい音で相手を誘惑するのに対し、ヒヒは視覚的な動物であり、ヒヒの身体的な求愛行動や性的な活力は人間にもそれと理解できるとクマーは記している。 しかもひどいことに、マントヒヒの体は半裸に見える、と彼は付け加えた。 オスはマントで肩を隠しているが、下半身を露出している(メスも同じく)。 なんて恥じらいのない動物なんだ、と人によっては思うかもしれない。
ヒヒは、預言者ムハンマドの言葉をまとめた『ハディース』で言及があるものの、オオカモシカやガゼル、オオカミ、さらには世間の嫌われ者、ハイエナまで、あらゆる野生動物が登場する豊かなアラブ詩文化に登場することはない。 アハメド・ボーグは、自身も文学者であり詩を発表したこともあるが、クマーの表現に酷似した説明をしながら笑う。「ヒヒは言葉にしても麗しくなく、食べてもまずい。だから詩人にも無視されたんだ」と彼はいう。
人間とヒヒの不安定な関係は続く。 サウジアラビアのヒヒは、わずか約65%が野生で、残りはタイフなど都市や町とその周辺に住んでいる。しかもタイフは国で有数のレジャー観光地だ。 町に住むヒヒは片利共生的な動物に分類される。つまり「私たちと相席」しているのである。要するに、程度の差はあれ人の食べ物に頼って生きている。
ボーグはタイフの南側にあるワディ・リヤに私を連れて行ってくれた。ここにはヒヒの生息環境のあらゆる要素が詰まっている。 谷は両側が急勾配の岩がちな崖になっており、近くにある小さなワジと泉はダム湖につながる。 ヒヒは野生のアカシアの実やアザミゲシ(Argemone mexicana)の多肉根を食べるが、毎朝地元のピクニック場であるルダフ公園に出かけ、残飯を求めて大小のゴミ箱をあさる。公園の管理人に追い立てられるまで、できるかぎりの餌を集めるのだ。
 |
| 餌が簡単に手に入るので、ヒヒの行動範囲は狭まる。そして人間と同じように、運動不足のヒヒは病気になる。 |
「ここでは片利共生が長い間問題になってきました」とボーグは語る。「でもここ30年はさらに悪化しています。環境問題を上回る勢いで開発が進んでいますから。」 ヒヒの個体数の4%、すなわち数千頭が今やに人間の食料に頼って生きている。
だがアル・ハダの運転手の例でわかるように、問題はヒヒが餌をあさることだけではない。 人間がヒヒに餌を与えているのだ。 「神に逆らった人間が罰を受けてサルやブタになったと思っている人もいるのです」。ボーグは語る。 「霊的な点数稼ぎをするために餌を与えるのです。」
彼は、町中のレストランやベーカリーから残り物を集めて、アル・ハダのヒヒに餌を与えているという地元民の話をしてくれた。 私はアル・シャファという、タイフの南の丘の、遊園地やピクニック場がある観光地に車で出かけた。そこでは観光客が道路脇の店から果物を買って、餌を待つヒヒに直接与えていた。
私はヤンブーという沿岸の町から来た3人の若者にわけを尋ねた。 「わからないよ」。一人が言った。 「考えたこともないさ。」
「良いことだからさ。神の慈悲のためにだ」ともう一人が言った。
森林に覆われた岩山と急落する峡谷の、息を呑むほど美しいパノラマが目の前に広がるアル・シャファの見晴台で、北の町ハイルから友人のフマイドと週末の小旅行に訪れていたスレイマンが、バーベキューの準備をしていた。
「ヒヒに餌をやるのは、祈りと断食の一部です」。彼は言った。「良い行いです。ヒヒには他に食べ物がありません。 食べ物が十分にあれば、人間のところには来ないはずですよね。」
こうした生物学的に見当違いの善意の介入が、ひどい状況を招いている。 野生ではマントヒヒの群れは合計で120頭ほどだが、片利共生的な群れでは800頭以上いた。餌を探す必要がなくなり、行動域が7~8平方キロに狭まった。野生ならばその3倍以上は動く。
 |
| マシュー・テラー |
| タイフに通じる道では、「動物にエサを与えないでください」という看板が。 |
この結果、過密状態となり社会的なストレスが生じる。 オスが大きくなりすぎた単雄群で秩序を保てなくなると、自由なメスは群れから離れて相手のいないオスと交尾し、そのオスが今度は合同でさらに多くのメスを手に入れる。 アル・ハダの片利共生的な群れで見られた尻尾をつかむ行為はストレスによるものだとボーグは言う。 野生ではそのようなことはない。 餌のやりすぎも出生間隔を狭め、過密状態を悪化させる。 そして塩分、糖分、脂質が高いジャンクフードの問題もある。 片利共生的なマントヒヒは、腸内に寄生虫が増えるなど健康を害するようになる。
問題は人間にも及ぶようになる。近くでヒヒが増えれば、ビルハルツ住血吸虫症や結核のリスクが高まる。 ヒヒはタイフ周辺の畑を襲い、作物を荒らし、フェンスや建物を破壊する。 ある群は陸軍基地を襲った。軍用車のシートを破り、レーダーのケーブルを咬み切った。 タイフでは交通事故も増えている。原因はハイウェーの動物だけではない。 2010年の『アラブニュース』紙では、ヒヒがトラックに投石し、タイフの男性が死亡したことが報道された。
ボーグは、とにかく人間に近すぎる場所で暮らすヒヒが多すぎることが原因だという。 彼はその理由をよく理解している。 森林伐採や過剰放牧による生息環境の断片化、ハンターがヒヒの天敵、とくにオオカミやヒョウ、ハイエナを殺していること――そうした要素が複合的に招いた事態だ。
ボーグの指示で、NWRCは片利共生に対策を講じ、ヒヒの野生状態を維持しようと努めている。 1990年代後半、NWRCはアブハーでヒヒの個体数を半減させることに成功した。これは2つの長期的なアプローチで実施された。 科学者は、出生率を下げるための精管切除やホルモン・インプラントを試み「人道的な間引き」を行った。そして当局者は公共の標識を掲げ、路上のエサやりに罰金を課す権限を警察に与えた。 人間の行動とヒヒの急増の両方に取り組むことが重要な意味を持つ。
| 天のサル? |
古代エジプトではマントヒヒが崇められた。 新王国時代(紀元前約1500年)には、現在のスーダンにあるヌビアと、紅海の南の海岸にあるプント国から、儀式目的でヒヒが持ち込まれていた。 エジプトの宗教において、ヒヒがどのような地位にあったのかは定かでないが、神々が宿る舟と人間の代わり、という2つの役割があったようだ。 壁画ではヒヒが舟を作り、収穫を行う様子が描かれている。ヒヒは国王の輪廻の過程でミイラとなった可能性もある。
マントヒヒとの関連で最もよく知られるのが、神の書士で知識の源であるトート神だ。また死者の心を宇宙の原動力と比べて均衡を図る均衡の神、アーンというサルに姿を変えたトート神もある。 マントヒヒはエジプトの画や彫刻にも多く登場する。太陽を崇拝している姿であることが多く、オスのヒヒが毛づくろいをしてもらっているときの、 頭を後ろにもたげ、腕を空に持ち上げた特徴的な姿勢がモデルになっているのではないかとの仮説がある。 |
「どちらも一緒に取り組まないとうまくいきません」とボーグは説明する。 「ヒヒを減らすだけでは解決にはなりません。他の野生のグループがやってきて、また片利共生になります。 人間にも餌やりを止めさせなければなりません。 その唯一の手段が、公共の意識向上キャンペーンなのです」
NWRCは高校での環境教育に資金を拠出し、新たにビジターセンターを開設した。 ボーグはタイフの政府役人を対象にヒヒの片利共生をめぐる問題について説明会を開き、環境要因を特定しながら持続可能な解決策について指導を行った。 昨年8月、彼は香港周辺でマカクの個体数を管理する長期的なプログラムが、避妊と法的介入を通じて大きな成功を収めた例を、参加した会議で学んだ。 ボーグはタイフで地方政府の承認を待ちながら、サウジアラビアでも同じ手法を実施するところだ。 だがそれも長い道のりになりそうだ。
アル・ハダに戻ると、車がハイウェーの路肩に7、8台並んでいた。横柄な銀のマントのオスに見守られて幼いヒヒがエサを頬張る様子を見ながら、車の中の人間が優しく語りかけているのだった。 オレンジのカバーオールを着た一人の自治体職員が、捨てられたペットボトルと食品の包装紙を拾っていた。
見慣れた光景である。 タイフとメッカの間を移動する商人や旅人は、昔からアル・ハダを経由していく。断崖をまたぐ古い石の道路は、近代ハイウェーに沿って今も健在だ。 学者のヤクート・アル・ハマウィは、1228年に著書『国の辞典』(原題:Mu’jam Al Buldan)の中でアル・ハダを説明しているが、そこに住むヒヒについても冷ややかに触れている。 インターネットで検索すると、ヒヒのおどけた姿の動画に対し、同じく不快感をあらわにしたコメントが多く寄せられていた。 「タイフに住んでいるが」とワリード・ジラニは記す。 「メッカやジッダに行くときはいつもヒヒに苦労するんだ。 だから別の道を通るときもある。」
正式なアラビア語では、ヒヒはクルドゥと呼ばれる。 ケチ、または安く生活する人を意味するこの言葉の語源は、「不運な」という意味の言葉だ。 だが口語では、ほとんど人がマントヒヒを、サダン(「幸せもの」と訳される)かルバー(「利益を得る者」という意味)と呼んでいる。 真水の泉が近くにあり、夜は岩がちな崖に守られた眠ることができるアル・ハダで、マントヒヒが善意の人々から餌をくすねる様子を見ていると、不確実な将来に備えて、ケチなりに喜んで利益を守っているかのようにも見えてくる。
| ヒヒはペットを飼うのか |
2011年、YouTubeに投稿された動画で、タイフのマントヒヒが野良犬を連れ去り、ペットとして飼っていた様子が紹介された。 この動画は驚くほど注目を集め、60万回以上も再生された。 この3分間のシーンは、フランスの制作班がナショナル・ジオグラフィック・チャンネルと共同で制作した「アニマルズ・ライク・アス」(私たちのような動物)でも取り上げられた。動物の行動を特集し多くの賞を受賞しているテレビシリーズである。 YouTubeのクリップでは、オスのヒヒが犬の尻尾をつかみ、小突き、土の上を引きずり回す様子を映している。カメラは次に、成犬とヒヒが共にくつろいでいるシーンへと変わり、ナレーターが語る。「連れ去られた子犬はヒヒの家族と共に成長し、寝食を共にしている」。 互いに毛づくろいをする穏やかなシーンが、心温まる音楽の高まりとともに消えていく。
連れ去りは、長い間ヒヒの正常な行動として理解されてきた。 オスは授乳中のメスから幼獣を奪おうとする。これはオスが群れの中での地位を高めようという戦略の一つだ。 だがヒヒがなぜ別の種を連れ去るのか。 感情を操るような音楽とナレーション、注意深く編集された映像はさておき、この脱文脈化されたビデオクリップは、犬と仲間になろうとするヒヒと、主人であるヒヒに応える犬を「本当に」映し出しているのだろうか。人間が自分を投影させているのではないのか。
共存は自然界でも珍しくない。 だがペットを飼うこと、つまりある種の動物が、別に明確な機能的理由もなく他の種を引き取り、責任をもって一生餌を与え面倒を見る例は、ほとんど知られていない。 捕われの環境以外では、ホモ・サピエンス だけに知られる行為である。 ゴリラのココが子猫を飼っていたことは有名だ。ケニアのカバは、ゾウガメと友達になった。他にもわずかながら例がある。だが、これらはすべて人工的な環境での出来事だ。 野生では西アフリカのチンパンジーが、ハイラックス(ネズミに似た小動物)を捕まえて短時間戯れるケースが観察されているが、やはり間もなく殺してしまい、エサにすることもある。
YouTubeの動画には、ウェスタン・カロライナ大学で人と動物の相互作用を専門に研究するハル・ヘルツォークも注目した。 『サイコロジー・トゥデイ』と『ハフィントン・ポスト』のコラムでは、複数の見解を照合しながらタイフのヒヒが犬をペットとして飼っていた可能性を探り、動画で美化されていた点に疑問を投げかけながら懐疑的な見方を呈した。
- 子犬はどれだけヒヒと一緒にいるのか。長期なのか、それとも一時的なのか
- ヒヒは子犬をかわいがったり遊んだりする以外に、子犬から何か利益を得ているのか。子犬にはどのような利益があるのか
- ヒヒは子犬を殺したり食べたりすることがあるのか
今のところ答えはわかっていない。 ジッダにある小さなボランティア組織、サウジ・アラブ・アメリカン・ヒヒ研究所の共同創立者、ジョン・ウェルズも同様の反応だ。 「私も懐疑的です。編集前の映像を見たいですね。」
だがウェルズは、動画のシーンは珍しいものではないと言う。ネコを世話するヒヒを見たことがあると説明した。 「アル・シャファで見た光景です。メスのヒヒ4頭が、鳴いている子猫のもとへ岩だらけの斜面を降りてやってきました。 子猫は急に鳴くのを止め、ヒヒにじゃれついたのです。 跳びはねて楽しそうでした。 その後オスが斜面を下りてきて、子猫を水飲みに連れて行くのです。」
ヘルツォークは、著作『好きな動物、嫌いな動物、食べる動物』(原題:Some We Love, Some We Hate, Some We Eat)の中で、ペットを飼うためには文化、つまり社会的な模倣と仲間の承認がなくてはならないことを断言する。 ストレスが多く過密な生息環境と、過剰な餌に悩むタイフの片利共生的なヒヒたちは、癒しを求めてペットを飼うのだろうか。 それともヒヒは思いやりの文化をつくっているのだろうか。 今は憶測しかできない。 |
翻訳記事に関するご意見ご要望
翻訳記事についてお気づきの点がありましたら、saworld@aramcoservices.comまでご連絡ください。今後の改善に役立てさせていただきます。ご送信の際は、件名を英語で “Translations feedback” としてください。多数のコメントをいただく場合、すべてのメールに返信できない可能性もありますので予めご了承ください。
--編集部 |