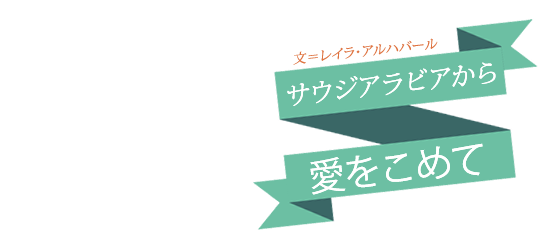
 |
| トビアス・コフナツキ/RAZORFILM |
| 主役を演じたワアド・ムハンマドの演技は世界的に高い評価を受けた。 上: 緑色の自転車を見つけ、絶対買うと心に決めたワジダ。 |
リヤドに暮らす10歳のワジダは、いつものように歩いて学校に向かう。そこへ近所の親友、アブドゥラが自転車でやってきて、ワジダのスカーフをふざけて奪う。 「取ってみろ」とからかうアブドゥラ。 「自転車があればね!」とワジダは叫んだ。 アブドゥラは「女は自転車なんて乗らないもんだろ」と言い返す。 彼の後ろ姿を見ながら、ワジダは決心した。 その後、お金をためて自分の自転車を買ったら競争を挑むとアブドゥラに伝えたワジダ。 母親と学校の反対を押し切ってワジダが追求する自転車の夢は、サウジアラビアの文化と慣習、そして世界共通の人間性を照らし出す豊かで重層的なストーリーへと展開する。
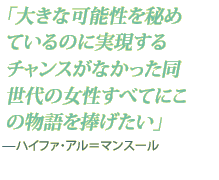 昨年の冬にリリースされてから世界各地で16の賞を受賞してきた映画『少女は自転車にのって』は、39歳のサウジアラビア人監督ハイファ・アル・マンスールが初めて手がけた長編映画である。また、すべてサウジアラビア国内で撮影され、キャストもすべてサウジ人、初の女性監督作、同国から初めてアカデミー賞に出品された作品としても話題を呼んでいる。
昨年の冬にリリースされてから世界各地で16の賞を受賞してきた映画『少女は自転車にのって』は、39歳のサウジアラビア人監督ハイファ・アル・マンスールが初めて手がけた長編映画である。また、すべてサウジアラビア国内で撮影され、キャストもすべてサウジ人、初の女性監督作、同国から初めてアカデミー賞に出品された作品としても話題を呼んでいる。
アル=マンスールは、映画の成功はサウジアラビアの社会的変化の賜物と考えている。 「10年前ならリヤドでこんな映画を撮ることはできませんでした」と監督。 「サウジアラビアの未来は、興奮と楽しみであふれています。この映画でそれが感じてもらえればいいですね」
 |
| トビアス・コフナツキ/RAZORFILM |
| リヤドでの撮影中に、アブドゥラ役のアブドゥラフマン・アル=ゴハニとワジダ役のワアド・ムハンマドにアドバイスするアル=マンスール監督。 |
映画は、サウジアラビアの中流家庭の内情に光を当てている。 ワジダはひとりっ子で、伝統あるイスラム女学校に通う。男の子のようなコンバースのスニーカーや、ポップスの音楽テープ、スポーツチームのチームカラーで編んだミサンガといったささやかな反抗は校長の受けが悪い。中でも自転車が欲しいという彼女のとっぴな願いは、校長の辛辣な非難を誘った。 ワジダの母親は人あたりのよい女性。暑くて時間がかかる通勤中は、短気な運転手のせいでイライラを募らせる。夫に惚れ込んでいるが、息子を授かる夢を第2夫人に託そうという夫の姿に深く傷つく。 ワジダの親友、アブドゥラは心優しく友だち想いのチャーミングな男の子。ワジダの家の屋上でこっそりと自転車の乗り方を教えてくれるなど、彼女の味方にもなってくれる。勝利と敗北がむき出しで、伝統と自由がせめぎあうサウジ社会に住むワジダとアブドゥラ。二人とも、社会が求めるジェンダー像にはまだ気づいていない。
「物語に登場する出来事は現実そのものです。あまりにも生々しく、偽りがないので、サウジ人として自分もショックを受けたくらいです。映画にありがちなごまかしも表面的な取り繕いもありませんから」と言うのは、アーティストのマナル・アル=ドワヤン。アル・マンスールと同様に、サウジアラビア東部州で育った女性だ。
アル=マンスールは、自転車が「実現できなかった夢の象徴で、 叶わぬ夢を実現しようと思ったことのある人なら誰でもワジダの軌跡に共感できると思います」と語る。 偶然にもサウジ国旗の色と同じ緑の自転車。アル=マンスールにとって、この自転車は、物理的にも社会的にも自由に動き回れることの象徴である。 若さにあふれる、昔ながらの「自転車は、おもちゃのようなものだけど、だからこそ脅威とか害になるものとは映らないはず」と指摘する。 ワジダの根気強さは堂々として魅力的だし、彼女が笑顔になれば見ているこちらも笑顔になる。 観る側はワジダの頑張りと厳しい試練に心を痛めるが、最終的には、母親の愛情がこもったさりげない行いによって社会の偏見を乗り超えていく。
そして自転車競争のシーンも、映画全体と同じように穏やかでありつつ、象徴的なシーンを描き出している。 ワジダがアブドゥラに「追いつけるものなら追いついてみて」と叫ぶシーンでは、自分だけでなく、同世代の声を代弁していたに違いない。
「少女は自転車にのって」は、結婚生活、家族、教育、仕事、宗教、そして愛についてこれまでにないないほど率直に描き、余すところなく共感を誘った点でシリアスな映画であるとも言える。 観客の心をゆさぶる人類共通の感情は、国籍、人種、宗教の違いをかすませる。 人気の高いアメリカの映画批評サイト、www.rottentomatoes.comでは、99%の高い批評家総合評価を得た。 『オレゴニアン』紙のマーク・モハンは「サウジの生活について、私たちが持つイメージと期待を覆してくれる奇跡的な映画」と評価し、 ウィスコンシン州ミルウォーキーの『ジャーナルセンティネル』紙のデュアン・デュレクは、ワジダを「権威に歯向かうというよりは、個性を発揮するという意味で、サウジのリサ・シンプソンのような少女」としている。 『デトロイトニュース』紙では、トム・ロングが「たしかにサウジアラビアを舞台とした作品だが、 それ以上に、人生をテーマとした作品である」と記している。
 |
| トビアス・コフナツキ/RAZORFILM |
| 自転車に乗れるようになりたいワジダに、ヘルメットを渡すアブドゥラ。こうしてワジダの決意を讃え、支えていく。 下: 2012年ドバイ国際映画祭で、ドバイのシェイク・マンスール・ビン・ムハンマド・ビン・ラーシド・アル・マクトゥーム首長から最優秀女優賞を受け取るワアド・ムハンマド。 |
だがサウジ女性にとって、この映画は他人ごとではないようだ。 東部州アルカシーム出身のディナ・ジュライファニは、「映画とまったく同じことを体験しました。今でもあることですが、家族の考え方でだいぶ違います」と語る。 同様に、アブドゥル役のアブドゥルラフマン・アル・ゴハニを甥に持つファッションデザイナーのダネ・ブアフマドは、「映画を観ていると欧米の人々がサウジをどう思うか心配になる箇所もありますが、少女と母親の感動の物語だから、女性なら共感できると思います。 サウジアラビアの現実を露わにし、多くの問題に触れつつ、人間味のある物語りになっています。 涙が溢れてきました。映画を観た人は皆感動すると思います。 サウジアラビアの出来事を取り上げながらも、誰もが共感できるストーリーに見事に仕上げたハイファは立派ですね」と語っている。
アル=マンスールはサウジアラビアについてこう説明する。「ジーンズも履くし、10代の若者は親に対して生意気ですよ。どこも一緒です。 知られていないストーリーもまだまだあります」 敬虔なイスラム教徒で、冷たく厳しい校長を演じるアフド・カメルは、自身もサウジ人映画監督である。彼女はこう語る。「私たちは人間ですから 愛も恐れも感じます。 サウジアラビアは白黒片方だけの社会ではありません。 民族も伝統も数多い、とても複雑な文化です」
世界各地の映画館や映画祭で上映され、アカデミー賞にも出品されたこの映画を、映画館のないサウジアラビアで観ることができないとは、なんとも切ない話ではないか。 多くの人を悩ます状況だが、サウジアラビア文化芸術協会のディレクター、スルタン・アル・バジエは、自身が委員長を努める協会の非政府ノミネート委員会が、アカデミー賞外国語映画賞のサウジアラビア初公式代表作品にこの映画を選んだことを歓迎している。 アル=バジエは、受賞のチャンスはあると信じている。 彼によると、映画芸術科学アカデミーは地元で作られたインディペンデント系の作品を評価する。「少女は自転車にのって」は「ストーリーに重みがあり、存在感に手応えがあるすばらしい映画だ。 世界の映画祭では多くの賞を受賞した。映画館がないこの国で現実に立ち向かったハイファの挑戦はもちろん、こうした挑戦も意義あるものだと思う」 そして、アル=マンスールは、サウジの映画制作者に新しいエキサイティングな世界を見せてくれた、と補足した。
それならば映画館ができる日もやがて来るのだろうか。 「サウジアラビア人はこれまでも衛星放送や海外旅行などの手段を通じて、映画、ファッションをはじめ、さまざまな芸術に触れてきました」とアル=バジエ。 「サウジ人は皆、映画に対して意見を持っています」 たしかにサウジ人はDVDを買ったりレンタルしたりするし、衛星やインターネットでダウンロードもする。海外に行けば映画館だって利用する。 だがこれについては、アル=マンスールも神妙な面持ちだ。 「女性の運転を禁じているのと似ています。 論争の多い問題です。賛成派も反対派も感情的になりますから。だからなかなか解決しないのです。 機が熟せばきっと実現するでしょう」 彼女によると、一番重要なのは、「文化的な規律を守りながら社会進出できるような女性が活躍できる場が広がった」ことだという。 まだ80年の歴史しかない伝統的で保守的な部族社会のこの国に、激しい抗議運動やキャンペーンで変化をもたらそうとしても効果は薄いと考えているようだ。
だから実際はこうである――サウジ人がよくやるように、アブドゥラティフ・アブドゥラディも、この映画をダウンロードして友人宅で鑑賞した。 「サウジアラビアの社会問題の多くに触れたすばらしい映画です。脚本もとてもカジュアルでスッキリとしています」
ストーリーの裏には多くのメッセージが隠れているが、アル=マンスールは、観客がストーリーを楽しみ、希望と意欲を感じてくれるのがささやかな望みだという。 「見終わった時に、夢を見ることの力強さと幸せを実感してもらえれば嬉しいです。 変化は努力で生まれるのですから」 アル=マンスールのメッセージに国境はない。
 |
レイラ・アルハバール(leila@alhabbal.net)は、サウジアラビアのダーランで「アラムコキッズ」として育った。フィリップス・エクセター・アカデミーで学び、ジョージワシントン大学でジャーナリズムを専攻した。 現在はダーランに住み、フリーライター、編集者として地域の社会問題を取り上げている。 |